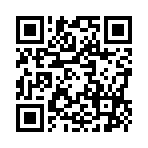2020年09月29日
黄色が
チャボホトトギス



随分涼しくなって来ました!
天候や雑事にかまけているうちにヒガンバナが目立つ頃になってしまいました。
秋の花か~ 今年は『チャボホトトギス』はどうだろう? 思い立って覗きに行ってみました。
いつもの所に散らばって有りますが開花しているのは3株程、それでも少し暗めの所に鮮やかな黄色が浮かび上がるように咲いているのが見つかると顔が緩みます。
ユリ科ホトトギス属の多年草。名前は寸詰まりで小型な点を鳥の「チャボ」に例えたと言われています。



随分涼しくなって来ました!
天候や雑事にかまけているうちにヒガンバナが目立つ頃になってしまいました。
秋の花か~ 今年は『チャボホトトギス』はどうだろう? 思い立って覗きに行ってみました。
いつもの所に散らばって有りますが開花しているのは3株程、それでも少し暗めの所に鮮やかな黄色が浮かび上がるように咲いているのが見つかると顔が緩みます。
ユリ科ホトトギス属の多年草。名前は寸詰まりで小型な点を鳥の「チャボ」に例えたと言われています。
2020年08月17日
予期せぬ
ミゾホウズキ



今日は珍しく『ミゾホウズキ』に出会う事が出来た。ただ以前の記憶に対して今回は随分と小さく感じたので一瞬別種ではないかと疑ってしまった。
極端に少ないという訳ではないが普段あまり出会うことの少ない花との予期せぬ出会いは結構うれしい!
茎は地を這う感じで広がり、花の長さは1~1.5cmと小さい。
ハエドクソウ科ミゾホウズキ属の多年草だが前の分類法では「ゴマノハグサ科」に分類されていた。



今日は珍しく『ミゾホウズキ』に出会う事が出来た。ただ以前の記憶に対して今回は随分と小さく感じたので一瞬別種ではないかと疑ってしまった。
極端に少ないという訳ではないが普段あまり出会うことの少ない花との予期せぬ出会いは結構うれしい!
茎は地を這う感じで広がり、花の長さは1~1.5cmと小さい。
ハエドクソウ科ミゾホウズキ属の多年草だが前の分類法では「ゴマノハグサ科」に分類されていた。
2020年08月06日
取り揃えて
タンキリマメ花

豆 果

タ ネ

葉の形

金網に絡んだ『タンキリマメ』が一連の姿を見せていた。
花が咲いて結実して鞘を作り、それがはじけて種まで。同じ所に一式取り揃えているのもちょっと面白いと思って撮ってみました。
ついでに葉の確認用も、葉の質は少し厚めで一番幅の広い所が中央より少し先端によった所になります。これは「トキリマメ」との識別ポイント。
マメ科タンキリマメ属で日当たりの良い所に生えるツル性の多年草。ツルに下向きの毛がある。
2020年07月06日
一日花
ハマボウ


我が家の鉢植えの『ハマボウ』が初めて2つ花を付けた。これは随分と前(10年以上?)久能山東照宮の階段入口あたりに有った木から種を拾って来て植えたものだと記憶している。
最低限の水やりだけでろくに世話もしなかったのによくぞ咲いてくれたものだ! ただこの花は一日花、二つ目の花が昨日の朝咲いて夕方には萎んでしまった。と云う事で今年の花期はあっけなく終了とあいなった。
アオイ科フヨウ属の落葉低木。本来の生育地は海岸や河口の砂泥地だが防砂林や庭木などにも使われる。
2020年06月25日
様々
エゴノキ若い果実


5月15日に満開の花を取り上げた『エゴノキ』は早くも若い果実を沢山ぶら下げていました。
植物は花が咲いてから果実が熟すまでの期間は種によって様々ですが比較的に早い部類に入るかもしれません。
もう少し熟すとカラが縦に割れ、中の種子はヤマガラの大好物、足で押さえて殻を割っている姿を時折見かけました。
ちなみにクスノキ科の「シロダモ」のように翌年の花が咲く頃にやっと前年の実が熟すと云うのんびりタイプも有るようです。


5月15日に満開の花を取り上げた『エゴノキ』は早くも若い果実を沢山ぶら下げていました。
植物は花が咲いてから果実が熟すまでの期間は種によって様々ですが比較的に早い部類に入るかもしれません。
もう少し熟すとカラが縦に割れ、中の種子はヤマガラの大好物、足で押さえて殻を割っている姿を時折見かけました。
ちなみにクスノキ科の「シロダモ」のように翌年の花が咲く頃にやっと前年の実が熟すと云うのんびりタイプも有るようです。
2020年06月09日
一斉に
ムラサキシキブ


山裾の道端に枝を差し出した『ムラサキシキブ』が一斉に咲きだしたと思ったらすでに茶色くなっている所もある。花の命は何とやらと言うところでしょうか。
小さな花も可愛らしいがどちらかと言うとこの木は紫色の果実の方が珍重されてよく植栽されたりする。
クマツヅラ科ムラサキシキブ属の落葉低木。 ちなみに果実が白く熟すものを「シロシキブ」と云う。


山裾の道端に枝を差し出した『ムラサキシキブ』が一斉に咲きだしたと思ったらすでに茶色くなっている所もある。花の命は何とやらと言うところでしょうか。
小さな花も可愛らしいがどちらかと言うとこの木は紫色の果実の方が珍重されてよく植栽されたりする。
クマツヅラ科ムラサキシキブ属の落葉低木。 ちなみに果実が白く熟すものを「シロシキブ」と云う。
2020年06月05日
アズサ
キササゲ花序


恐らく植栽されたものだと思いますが、金網を隔てた雑木の中で『キササゲ』が咲き始めていました。ただ高い木の上のほうなので無理かと思ったが一房だけ私にも処理できそうな所に咲いていたので撮らせてもらいました。
キササゲは古くに中国から入ってきたと云われ、植栽によく使われていますが、川岸など陽当たりのいい所に野生化もしている様です。
ノウゼンカズラ科キササゲ属の落葉高木で高さは5~15mになります。別名は「アズサ」
2020年06月03日
落ちずに
クスダマツメクサ


土手下の道端に数年前から居をかまえた『クスダマツメクサ』は、殖えもせず減りもせず今日も花を付けている。
他の草もあまり生えず、けっして環境はいいとは云えない所で命をつないでいる。
マメ科シャジクソウ属でヨーロッパ原産の一年草。
小さな花が沢山集まって花序を作り、花は受粉した順に下を向き花弁は大きくなるが落ちずに種子を包んでいる。


土手下の道端に数年前から居をかまえた『クスダマツメクサ』は、殖えもせず減りもせず今日も花を付けている。
他の草もあまり生えず、けっして環境はいいとは云えない所で命をつないでいる。
マメ科シャジクソウ属でヨーロッパ原産の一年草。
小さな花が沢山集まって花序を作り、花は受粉した順に下を向き花弁は大きくなるが落ちずに種子を包んでいる。
2020年05月15日
存在に
エゴノキ 花



この花の存在に気付くのは大抵が林道などに、真ん中がスポッと抜けた花が大量に落ちている時、
頭上を見上げるとまだ花は残っていても大分上の方だったりして結局コンデジを向けずに終わってしまう事になる。
今回は手の届く所に花の落ちる前の個体にお目に掛かることが出来たので無駄なシャッターをこれでもかと切らせて頂きました。
エゴノキ科エゴノキ属の落葉小高木で株立ちになり、高さは7~8m程になる。
少し離れた所ではアオキに絡んだ「スイカズラ」も花盛りになっていました。少しピークを過ぎたようで黄色くなった花が目立ちます。
スイカズラ科スイカズラ属で半常緑のツル性木本。別名は「キンギンカ」
スイカズラ


2020年05月03日
平開しない
ミツバウツギ 花序

ミツバウツギ花が密集しているタイプ

獲物を待つハナグモ

イペの木(ブラジルの国花)

あちこちのお庭で「イペ」の鮮やかな黄色が目立つようになりました。
林縁の『ミツバウツギ』も盛んに花を付けていますが、枝が見えなくなるほど沢山の花が密集して咲いているものも有ればすっきりしているものもある。
花に近寄って見ると「ハナグモ」がツボミに似たおしりを上に向けて獲物を待っていた。
花弁のように大きく開いているのはガク片で花弁も5枚有るが平開しない。
ミツバウツギ科ミツバウツギ属の落葉低木。名前に「ウツギ」と入っているがウツギはユキノシタ科