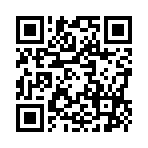2020年08月17日
予期せぬ
ミゾホウズキ



今日は珍しく『ミゾホウズキ』に出会う事が出来た。ただ以前の記憶に対して今回は随分と小さく感じたので一瞬別種ではないかと疑ってしまった。
極端に少ないという訳ではないが普段あまり出会うことの少ない花との予期せぬ出会いは結構うれしい!
茎は地を這う感じで広がり、花の長さは1~1.5cmと小さい。
ハエドクソウ科ミゾホウズキ属の多年草だが前の分類法では「ゴマノハグサ科」に分類されていた。



今日は珍しく『ミゾホウズキ』に出会う事が出来た。ただ以前の記憶に対して今回は随分と小さく感じたので一瞬別種ではないかと疑ってしまった。
極端に少ないという訳ではないが普段あまり出会うことの少ない花との予期せぬ出会いは結構うれしい!
茎は地を這う感じで広がり、花の長さは1~1.5cmと小さい。
ハエドクソウ科ミゾホウズキ属の多年草だが前の分類法では「ゴマノハグサ科」に分類されていた。
2019年05月11日
変化が
コミヤマスミレ


葉裏は紫色を帯びる

気温は上がって日中は暑い程になった。車もエアコン始動です。
数あるスミレの中でも花期のもっとも遅いスミレの一つと云われている『コミヤマスミレ』の様子を見に行ってみました。
林道脇の崩れそうな斜面に点々と咲いていましたが若干ピークは過ぎたようで花の新鮮味は今一と云った所です。それと暗めの所が好きな事でも知られたスミレと云う事でコンデジ片手に大苦戦!
スミレ科スミレ属で葉の表面の色は変化が激しく、斑入のものもある。裏面は紫色を帯びるがこれも濃淡の変化が多い。 日本特産種でガク片が反り返る特徴が有る。
2019年04月07日
蜜弁
トウゴクサバノオ


そろそろツバメの初見が取り沙汰される頃になって気温もグッと上がりました。車は窓を全開です。
そんな陽気に誘われて『トウゴクサバノオ』の様子を見に行ってみましたが残念、どうやら遅きに失したようです、開いているのは1個だけ、後は皆つぼんでいました。と云う事で今回唯一無二の花です。
キンポウゲ科シロカネソウ属の多年草。花は直径8ミリ程で花弁状に見えるのはガク片。本来の花弁は蜜の分泌を専業とする黄色い蜜弁になっています。


そろそろツバメの初見が取り沙汰される頃になって気温もグッと上がりました。車は窓を全開です。
そんな陽気に誘われて『トウゴクサバノオ』の様子を見に行ってみましたが残念、どうやら遅きに失したようです、開いているのは1個だけ、後は皆つぼんでいました。と云う事で今回唯一無二の花です。
キンポウゲ科シロカネソウ属の多年草。花は直径8ミリ程で花弁状に見えるのはガク片。本来の花弁は蜜の分泌を専業とする黄色い蜜弁になっています。
2018年11月25日
赤い集合果
スルガテンナンショウ果実

いよいよ夜具も変わって冬の兆しが見え隠れするようになった。林道も日陰に入ると冷気が入ってくる。
そんな林道わきで『スルガテンナンショウ』の果実が派手に自己主張している。枯葉色が多くなったなかで赤い集合果は否応なしに目に飛び込んでくる。
この仲間の雄花はオシベだけ、雌花は子房が並んでいるだけ、花弁などは一切なくシンプルこの上ないが果実はしっかりできる。
サトイモ科テンナンショウ属の多年草。地下の球茎の大きさによって性転換する。
2018年11月09日
竜脳は
リュウノウギク

朝から雨です。と云う事で昨日載せようか迷っていた『リュウノウギク』を載せる事にしました。
林道の日当たりのよい斜面に咲いているのですが、どれも計ったように2メートルを越える高さなのでアップに耐えるものが撮れませんでした。これが昨日迷った理由です。では何故今日ならいいのか?と云われると・・・お天気でしょうか
キク科キク属の多年草。名前は葉を揉むと竜脳に似た香りがする事から「竜脳菊」となったようです。竜脳は樟脳の香りに似ています。
2018年09月24日
突き出して
シモバシラ


この2,3日秋らしい過ごし易い日が続いている。
山の林道沿いに『シモバシラ』が丁度咲き始めていた。まだ9割方ツボミだが咲き始めれば早いと思う。
先頭の花穂の片側に縦に並んだ花は4本のオシベと先が2つに割れたメシベ共々花冠の外に長く突き出している。
シソ科シモバシラ属の多年草。茎は四角で葉は対生。シソ科には香気の有るものが
比較的多いが本種に香気はない。


この2,3日秋らしい過ごし易い日が続いている。
山の林道沿いに『シモバシラ』が丁度咲き始めていた。まだ9割方ツボミだが咲き始めれば早いと思う。
先頭の花穂の片側に縦に並んだ花は4本のオシベと先が2つに割れたメシベ共々花冠の外に長く突き出している。
シソ科シモバシラ属の多年草。茎は四角で葉は対生。シソ科には香気の有るものが
比較的多いが本種に香気はない。
2018年08月07日
葉と歯
ウバユリ



もうそろそろかなと『ウバユリ』の開花に見当を付けて出掛けてみたが、どうやら遅きに失した感がある。もともとキリッと引き締まった花では無いので時を逃すとたちまちダラケタ感じに成ってしまう。いつもの事だが花の盛りに出会う事の難しさを痛感。
名前は漢字にすると「姥百合」で花期に葉が枯れている事が多いので「葉(歯)が無い」の語呂合わせで付けられたようですが、立派な葉が付いているものも結構ある。
ユリ科ユリ属の多年草。茎の高さは0.6~1メートル程。分布は関東地方以西、四国、九州。
2018年07月14日
青い果実
マルミノヤマゴボウ

暑さから逃れたくて林道を走って来ました。木々は葉を茂らせて陽ざしは遮ってくれますが見透しは悪くなります。
そんな林道沿いで存在感を示していたのは『マルミノヤマゴボウ』早くも青い果実が出来ています。
空き地や道端などで見かける「ヨウシュヤマゴボウ」は果序が垂れ下がりますが、こちらは潔く直立しています。
ヤマゴボウ科ヤマゴボウ属の多年草。果実は黒紫色に熟し、液果で果汁は紅紫色
2017年12月22日
地中が
シモバシラの霜柱


林道のあまり日の当たらない斜面は花期も果期も過ぎた草達の枯れ姿がもつれ合っている。
そんな中にシソ科のシモバシラも有って午後になっても昨夜の霜柱を残していた。さすがに早朝の鋭さはないが少し離れてもそれと分かる大きさです。
これは地上部は枯れているが地下の根はまだ枯れておらず、吸い上げた水分が凍って茎を破り次々に凍って出来たものです。この現象も地中がまだ暖かい内だけで、地中も凍ってしまうと見られなくなります。
2017年11月05日
翌年に
シロダモ 雄株

雄 花

今日は少し気温が下がって日が陰るとすずしく感じます。
林道沿いの『シロダモ』が花を付けていました。ただ花期は終盤に入っていてもう一つ気に入りませんでしたが取りあえず、
そしてこの木は花が咲いて果実が熟すのは翌年になるので雌株では花と一緒に
赤く熟した果実も見る事が出来ます。
クスノキ科シロダモ属の常緑広葉樹で雌雄別株。高さは10~15mになる。葉の裏は白く、3脈が目立ちます。