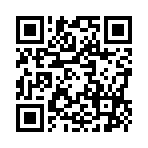2020年06月09日
一斉に
ムラサキシキブ


山裾の道端に枝を差し出した『ムラサキシキブ』が一斉に咲きだしたと思ったらすでに茶色くなっている所もある。花の命は何とやらと言うところでしょうか。
小さな花も可愛らしいがどちらかと言うとこの木は紫色の果実の方が珍重されてよく植栽されたりする。
クマツヅラ科ムラサキシキブ属の落葉低木。 ちなみに果実が白く熟すものを「シロシキブ」と云う。


山裾の道端に枝を差し出した『ムラサキシキブ』が一斉に咲きだしたと思ったらすでに茶色くなっている所もある。花の命は何とやらと言うところでしょうか。
小さな花も可愛らしいがどちらかと言うとこの木は紫色の果実の方が珍重されてよく植栽されたりする。
クマツヅラ科ムラサキシキブ属の落葉低木。 ちなみに果実が白く熟すものを「シロシキブ」と云う。
2019年11月07日
流れに
ミゾソバ

開花

群落

近所の水路と川の中間のような流れに『ミゾソバ』が大繁茂して花の盛りを迎えていた。水気の多い所でよく見かける草本だがこれだけ殖えるとなかなか見ごたえがある!
花は枝先にまとまって付き、開く前は金平糖のような感じに寄り集まっている。
タデ科イヌタデ属の一年草。茎には下向きの刺が有り、下部は地を這う。
2019年09月17日
半分に
ミゾカクシ

半分にカットした様な花


田んぼの隅に小さな白い花が散らばっていた。いったん通り過ぎたが戻ってみると『ミゾカクシ』でした。田んぼの雑草ですが近頃案外見る機会が減ったように思う。
花は上から見ると半分にカットしたような一風変わった形をしています。
キキョウ科ミゾカクシ属の多年草。キキョウ科の花は整った形の花が多い事からすれば、ミゾカクシの仲間は異端と云えるかも知れない。
茎は地を這って長く延び節から根を出して繁茂する事から「溝隠」の名が付いたと云われている。
2019年09月14日
質が薄く
トキリマメ


トキリマメの葉はタンキリマメに比べ小葉がやや大きく質が薄く、幅は下半部がもっとも広い。

近所の山裾の藪に絡んだ『トキリマメ』が葉陰に小さな花を沢山付けている。うまい具合に藪払いの鎌を掻い潜ったようだ。
花も豆果も豆も「タンキリマメ」にそっくりだが葉の質や形が微妙に異なることで識別できる。と云う事で別名は「オオバタンキリマメ」となった。
マメ科タンキリマメ属のツル性の多年草。ちなみにトキリマメの名前の由来は不明。
2019年07月10日
後に赤色を
ペラペラヨメナ 真上から


水量豊かな水路の両壁に居を構えた『ペラペラヨメナ』。いつ頃根付いたか定かではありませんが年々その領域を広げ、同じく外来種の「ヒメツルソバ」とその覇を競っています。
もともとは観賞用に導入されたようですが1949年に野生化が確認されてから関東以西にとびとびに帰化している様です。
キク科ムカシヨモギ属の多年草で原産地は中央アメリカ。花の色ははじめ白いが後に赤色を帯びる。ヒメジョオンなどと同属です。
2019年07月05日
実栗
ミクリ

クリのイガに見立てられた集合果

花穂、白い糸状のものは雌しべの柱頭、上の丸いのが雄花のツボミ

近所の半分水路のような川に『ミクリ』が実を付けていると出先で聞き、帰りに確認してきました。
なるほど情報通り結構な数の株が実を付けている、ここは割合とよく通る道沿いなのにどうして気付かなかったのだろう。注意力が散漫になったのか、視力が衰えたのか、いずれにせよ嘆かわしい。
花もまだ残っていて所々に散見できる。花茎は上部で枝分かれし、その枝の下部に雌頭花、上部に雄頭花を複数付けている。
ミクリ科ミクリ属の多年草で浅い水の中に生える。ミクリの名前はこの集合果を栗のイガに見立てて「実栗」の名が付いたと云われています。
2019年04月29日
普通種
コゴメウツギ


ここに来て肌寒い日が続いていささか戸惑いを覚える。
近所の山裾では「マルバウツギ」や『コゴメウツギ』が咲き始めている。両方ともよく見る普通種だが花が咲けばそれなりに華やぐ。
コゴメウツギはウツギの名が入っているがウツギの仲間ではありません。
バラ科コゴメウツギ属の落葉低木で叢生し、花は花弁もガク片も白いが長い方が花弁で短い方がガク片です。
2019年04月15日
栄養が
ウラシマソウ


林の中や林縁など比較的半日陰で見かける事の多い『ウラシマソウ』ですが山裾の結構な陽の当たる場所にも姿を見せていました。そのせいか葉の形が日陰のものより細く感じます。
サトイモ科テンナンショウ属の多年草。雌雄別株だが性転換する。初め雄株だが地下の球茎に栄養が貯まってくると雌株になる。
2019年03月19日
細長い
ジロボウエンゴサク


気が付けば日脚も大分のびて、花の便りも増えてきました。
山裾の道端では『ジロボウエンゴサク』が「ホトケノザ」と共にうらうらと咲いて小さな風をやり過ごしています。
花柄は細長い花の真ん中あたりに付いて後ろに距が長く突き出ている。子供たちはここを引っかけて遊んだようだ。
ケシ科キケマン属の多年草。地下に1センチ程の丸い塊茎がある。
2019年03月05日
そう果に
コオニタビラコ


「春に三日の晴れ無し」の言葉どおり雨が多くて参りますが、今日は朝から晴れて気持ちが良かった!
午後、ママチャリでえっちらおっちら出かけてみると田んぼは『コオニタビラコ』が一斉に咲きだしていました。
この花、田んぼによっては全く生えていなかったりしますが、恐らくそう果の形態に左右されているのかも知れません。
キク科タンポポ亜科ですがタンポポのようにそう果に冠毛が有りません。したがって風に乗って遠方まで旅をする事が出来ないのです。
タンポポ亜科でそう果に冠毛が無いのはこのヤブタビラコ属だけです。