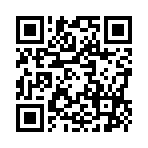2017年10月31日
形が
ダイモンジソウ



絶え間なく水の滴る、と云うか雨の後だけに流れ落ちるような状態の崖にびっしりと張り付いて今年も『ダイモンジソウ』が咲いていました。
長雨に足止めをされていたので花の盛りは少々過ぎてしまいましたが何とか間に合いました。気が付けば足元は水浸し。
名前は花を見れば云うまでも有りませんが、花の形が大の字に見えるので「大文字草」となった。
ユキノシタ科ユキノシタ属の多年草。花茎の高さは10~30cm程。
2017年10月30日
雄花も
キチジョウソウ

上から4つがメシベの退化した雄花その下のメシベが突き出ているのが両性花

吉事が有ると咲くと云う伝説に由来すると云う『キチジョウソウ』 どこかの誰かに吉事が有ったのでしょう。今年も暗めの林床でひっそりと咲いていました。
ちなみに漢字では「吉祥草」となります
花としては後半に入ったようで花序の上部まで咲ききって雌しべの退化した雄花も見られます。
キジカクシ科キチジョウソウ属の常緑多年草。花茎の高さは8~12cm。
2017年10月27日
内に巻いて
ノ ダ ケ


先日の風雨に茎が傾いてしまった『ノダケ』は茎の先端部をしっかり方向修正して
花序を広げていました。
紫色の小さな花のオシベと花弁は最初内に巻いていて、開花するとオシベのほうがはるかに長い。ちなみにセリ科の多くは白花を付け、紫色のものはごく少ない。
セリ科シシウド属の多年草で高さは80~150cm
2017年10月23日
油を
アブラススキ

台風一過、青い空に白い雲が浮かんで気持ちのいい日になりました。土手斜面では『アブラススキ』が高く抜きんでた割に所在無げに小穂をたらしています。
茎や花序の軸から粘液を出して油を塗ったような部分ができるのでこの名前が付いたようです。
イネ科アブラススキ属の多年草で高さは90~120cm。
2017年10月16日
時々4裂も
アケボノソウ 10月12日撮影

花冠が4裂の花と5裂の花が並んでいます。

先日「アケボノソウ」を12日に見に行って来ましたが、もう一つ気に入らなかったので撮り直しに行こうと思い、載せるのを止めたら次の日から連日の雨で足止めをされ、この先もハッキリしない予報なので取りあえず載せる事にしました。
花冠は基部近くまで深く5裂するが時々4裂のものもあります。径は2cm程で裂片にある緑色の2点は蜜腺溝で此処から蜜が分泌される。
リンドウ科センブリ属の2年草で山の湿った所を好みます。高さは60~90cmほど。
2017年10月11日
テレトリーを
ヤマトリカブト



この所季節が逆行して気温は30℃近辺の日が続いて暑い。それでも林道沿いの斜面からはトリカブトが点々と花を付けた茎をのばして山は秋模様。
一口にトリカブトと云っても何種も有りますがこの辺りは『ヤマトリカブト』がテレトリーを預かっているようです。
キンポウゲ科トリカブト属。「ヤマトリカブト」は日本産トリカブトの中では最も知られた名前ですが分布は意外と狭く、関東地方西部と中部地方東部の特産種との事です。
2017年10月09日
片側に
シモバシラ


林道沿いの林縁などに『シモバシラ』の花が盛りを迎えていました。雄しべも雌しべも
長く花冠の外に突き出して片側に並んで咲いています。
この一風変わった名前は冬に枯れた茎の根元に氷の造形物を作る事から
付きました。
この現象は外気が氷点下になって地上部は枯れますが地中の根はまだ生きていて水を吸い上げ、この水が枯れた茎の割れ目などからしみ出し、外気に触れて氷ができると云う仕組みです。ただこの現象も最初の頃だけで次第に地中も凍ってしまい氷の花は見られなくなります。
シソ科シモバシラ属の多年草で山地の木陰などに生えて高さは40~90cm。
2017年10月05日
ブラシのように
イヌショウマ


除草作業から免れた『イヌショウマ』が山裾の少し暗めの道沿いで何本か花を付けていた。
この花も開くとすぐにガク片と花弁が落ちてしまうので沢山のオシベと短いメシベだけになってブラシのようになる。
キンポウゲ科サラシナショウマ属の多年草で高さは50~80cm。
葉は2回3出複葉。
2017年10月02日
密集して
ヌルデ

ヌルデ め花

枝先に大きな花序を出して『ヌルデ』が花盛りです。しかしそう言われてもすぐには納得出来ないと思う。数え切れないほど付けた花の径は4ミリ程と小さいうえに密集して咲くので少し離れると形が分からなくなる。
花期は結構ルーズで早く咲いた個体はすでに青い果実を付けている。平地から低山までごく普通に見られる木だが秋の紅葉は結構きれいです。
ウルシ科ウルシ属の落葉小高木で大きくなると10メートル程になる事もある。雌雄別株。