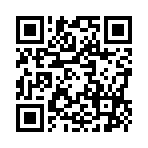2020年01月26日
張り付くように
クサボケ

1月も末になってやっと写真を撮る気力が少し戻ってきた。暮れから正月にかけて絶不調を極め、
不本意な正月を過ごすことになってしまいました。
まあそれは兎も角として昨年末に草刈をした土手斜面に『クサボケ』が結構広い範囲に広がって花を付けている。そのままにしておけば1m程に成長するはずだが毎年定期的に草刈をされるので一様に地に張り付くように咲いている。ただ盛りが過ぎてしまったようで形の好いものが少ない。
バラ科ボケ属の落葉小低木。クサボケの花は雄花と両性花が混じりあって咲き、小枝は刺になりやすく、葉には扇形の托葉が目立ちます。
2018年09月18日
ずい柱を
ガガイモ


土手下の植え込みに絡んだ『ガガイモ』がまだ花を付けている。例年は大抵8月の下旬に取り上げているから今年は大分遅れたのではないだろうか?
ガガイモの花は内側に白い毛を密生し見た目にも変わっているが大きな特徴はオシベとメシベが合着して「ずい柱」を作る事。
キョウチクトウ科ガガイモ属のツル性多年草。地下茎を長くのばして殖える。
2018年09月08日
白蝶草
ヤマモモソウ


葉と茎

情報を頼りにマイフィールドより大分河口よりの土手下に帰化植物を探しに行ってみました。
すぐに見つかりました。アカバナ科の『ヤマモモソウ』別名「ハクチョウソウ」最近こちらの方が正式名になった云う方もいます。
明治の頃に観賞用として入って現在も栽培されていますがこういう所にあるものは播種されたものに由来しているのではと云われています。それでも最近は帰化植物図鑑にも掲載されるように成りました。
それではとコンデジを向けるとそれ程強くはないが休む事無く吹く風が神経を揺さぶります。時計を見ながら辛抱たまらず撮っては見たが結局意図するものにはなりませんでした。( いつもの事か ) (>_<)
北アメリカ原産の多年草。高さは1~1.5mになる。
2018年06月27日
食草
ウマノスズクサ


サナギになる直前のジャコウアゲハの幼虫

今年は草刈のタイミングもあって少し遅れていた『ウマノスズクサ』の花が丁度咲き始めチラホラと葉陰に見え隠れするようになった。この一風変わった花は3個のガク片が合着して筒状になったものと云われる。
ウマノスズクサ科ウマノスズクサ属のツル性多年草。ウマノスズクサはジャコウアゲハの食草と云う事で近くにジャコウアゲハが数頭訪れていた。注意して見るとイタドリの葉の裏にはサナギになる直前の幼虫が静止していた。
2016年06月19日
ラッパ形の
ウマノスズクサ

内側に向いた毛が密生

日曜日の河川敷はGゴルフの大会のようでシニアの方々でにぎわっています。
その横土手斜面では『ウマノスズクサ』の2つ並んだラッパ形の花がまるでファンファーレでも奏でてくれている様に咲いていました。
ウマノスズクサ科ウマノスズクサ属のツル性多年草。花には花弁は無く、3個のガク片が合着してラッパ型になり、その先端部には内側に向いた毛が密生して虫が入りやすく出にくくなっている。 ただ食虫植物でもないのにどうして出にくくなっているのか今一つ解せない。
2015年04月27日
角ばって
アマドコロ


ノビル採りのおばさんに踏まれながら今年も『アマドコロ』が花を付けていました。やや盛りは過ぎたでしょうか? ただ個体数は増えたように見えます。
同じような咲き方をする「ナルコユリ」とよく比較されますがナルコユリの茎は丸く、こちらの茎は角ばっています。
この所気持ちの良い日が続いてなにかと助かります。
2014年05月06日
鋭い刺
ジャケツイバラ


道路沿いの土手の藪で『ジャケツイバラ』が咲き始めていた。
30cm程の花序によく目立つ黄色の花を沢山付けていかにも人目を引くが
油断は禁物、下手に手を出すと鋭い刺で痛い目に合う。
花は蝶形花ではなく5枚の花弁からなり上側の1枚だけ小さくて赤い筋が有る、雄しべは10個とも離生している。
と云う事でマメ科の中でも「ジャケツイバラ亜科」として分類される。


道路沿いの土手の藪で『ジャケツイバラ』が咲き始めていた。
30cm程の花序によく目立つ黄色の花を沢山付けていかにも人目を引くが
油断は禁物、下手に手を出すと鋭い刺で痛い目に合う。
花は蝶形花ではなく5枚の花弁からなり上側の1枚だけ小さくて赤い筋が有る、雄しべは10個とも離生している。
と云う事でマメ科の中でも「ジャケツイバラ亜科」として分類される。
2013年06月28日
最も強害な
イチビ

この所、梅雨仕様の空模様が続いて気分も曇りがち、それでも今日は午後になって久々にお日様が顔を見せてくれた。
そんな明るさにつられフィールドから少し足を延ばして見た。
さほど変わりばえのしない土手だがフィールドには無い『イチビ』が数本、黄色い花を付けていた。
古い時代には強靭な茎の皮から繊維を採る為に栽培もされていたようだが、最近では飼料畑や畑地に広範に発生し最も強害な雑草として名をはせている。
ただ、昔の「イチビ」と今のもの(輸入飼料などに混入して侵入したもの)
とは系統が異なると云われている。
アオイ科イチビ属の一年草でインド原産と云われている。

この所、梅雨仕様の空模様が続いて気分も曇りがち、それでも今日は午後になって久々にお日様が顔を見せてくれた。
そんな明るさにつられフィールドから少し足を延ばして見た。
さほど変わりばえのしない土手だがフィールドには無い『イチビ』が数本、黄色い花を付けていた。
古い時代には強靭な茎の皮から繊維を採る為に栽培もされていたようだが、最近では飼料畑や畑地に広範に発生し最も強害な雑草として名をはせている。
ただ、昔の「イチビ」と今のもの(輸入飼料などに混入して侵入したもの)
とは系統が異なると云われている。
アオイ科イチビ属の一年草でインド原産と云われている。
2012年07月13日
野性化
オニユリ

今年は何故か草刈りが遅れている切通しの土手斜面に『オニユリ』が今年も沢山ツボミを付けて立っている。今日はその中の2本が開花していた。
オニユリは古くから栽培され、しばしば人里近くに野生化が見られる。
元々は「鱗茎」を食用にする為持ち込まれたと云われ、原産地は対馬から朝鮮南部と考えられているようです。
ユリの仲間の鱗茎は毎年「鱗片」の数を増やして肥大化する。この鱗片は葉が多肉化したものでデンプン質に富んでいてオニユリの他「コオニユリ」や「ヤマユリ」など古くから「ユリ根」として食べられてきた。
そろそろ梅雨明けが待たれるこの頃です。

今年は何故か草刈りが遅れている切通しの土手斜面に『オニユリ』が今年も沢山ツボミを付けて立っている。今日はその中の2本が開花していた。
オニユリは古くから栽培され、しばしば人里近くに野生化が見られる。
元々は「鱗茎」を食用にする為持ち込まれたと云われ、原産地は対馬から朝鮮南部と考えられているようです。
ユリの仲間の鱗茎は毎年「鱗片」の数を増やして肥大化する。この鱗片は葉が多肉化したものでデンプン質に富んでいてオニユリの他「コオニユリ」や「ヤマユリ」など古くから「ユリ根」として食べられてきた。
そろそろ梅雨明けが待たれるこの頃です。
タグ :植物