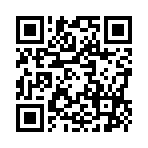2011年11月30日
周年
オニタビラコ


いつでもどこでも、そんなイメージの強い『オニタビラコ』、春から秋まで、と云うか暖かい
静岡では周年見る事が出来る。
畑の縁や空地はもとより市街地の植え込みの中やアスファルトの隙間まで幅広く姿を見せます。
名前は漢字にすると「鬼田平子」となり、鬼は大型の意味で田平子は「コオニタビラコ」の別名。と云う事で「コオニタビラコ」に似ているが大型なのでこの名になりました。
キク科タンポポ亜科オニタビラコ属で茎や葉を切ると白い乳液が出る。痩果には白い冠毛があり、よく飛んで空地等を渡り歩きます。


いつでもどこでも、そんなイメージの強い『オニタビラコ』、春から秋まで、と云うか暖かい
静岡では周年見る事が出来る。
畑の縁や空地はもとより市街地の植え込みの中やアスファルトの隙間まで幅広く姿を見せます。
名前は漢字にすると「鬼田平子」となり、鬼は大型の意味で田平子は「コオニタビラコ」の別名。と云う事で「コオニタビラコ」に似ているが大型なのでこの名になりました。
キク科タンポポ亜科オニタビラコ属で茎や葉を切ると白い乳液が出る。痩果には白い冠毛があり、よく飛んで空地等を渡り歩きます。
タグ :植物
2011年11月29日
目安
スイセン

東向き土手斜面の裾で『スイセン』が咲き始めていた。
歳の瀬へのカウントダウンは年賀ハガキの発売あたりから始まると思いますが、その先の目安として「スイセン」の開花もその一つに入れたい。このあと暦は「師走」となりせわしさは一段と加速するのでしょう。そして「ロウバイ」の花でも咲けば新しい年は目前となる。
「スイセン」の原産地は地中海沿岸。古い時代に中国を経て入って来たと云われていて、
越前海岸や爪木崎などは群生地として知られている。
和名は漢名の「水仙」をそのまま音読みして付けられた。

東向き土手斜面の裾で『スイセン』が咲き始めていた。
歳の瀬へのカウントダウンは年賀ハガキの発売あたりから始まると思いますが、その先の目安として「スイセン」の開花もその一つに入れたい。このあと暦は「師走」となりせわしさは一段と加速するのでしょう。そして「ロウバイ」の花でも咲けば新しい年は目前となる。

「スイセン」の原産地は地中海沿岸。古い時代に中国を経て入って来たと云われていて、
越前海岸や爪木崎などは群生地として知られている。
和名は漢名の「水仙」をそのまま音読みして付けられた。
タグ :植物
2011年11月28日
うすいピンクの
ウスベニニガナ


いつものフィールドより少し河口側へ下った土手斜面に「ナルトサワギク」らしき花が沢山咲いているので確認してほしいとの依頼を受けて早速行って見ました。友人の云う通りまさしく「ナルトサワギク」でした。
このキクは20年程前に県西部で確認され、近年安倍川水系でも確認されたと聞いていましたが、本格的に参入していました。
そのそばの土手斜面に作られた石段の隙間に『ウスベニニガナ』が幾つも咲いていました。この花も以前は四国、九州などが主な分布域でしたが、最近は静岡でもよく見かけます。
花は舌状花がないので目立ちませんがうすいピンクの可愛らしい色をしています。
今日は朝からずっと曇が厚く、肌寒い一日でした。


いつものフィールドより少し河口側へ下った土手斜面に「ナルトサワギク」らしき花が沢山咲いているので確認してほしいとの依頼を受けて早速行って見ました。友人の云う通りまさしく「ナルトサワギク」でした。
このキクは20年程前に県西部で確認され、近年安倍川水系でも確認されたと聞いていましたが、本格的に参入していました。
そのそばの土手斜面に作られた石段の隙間に『ウスベニニガナ』が幾つも咲いていました。この花も以前は四国、九州などが主な分布域でしたが、最近は静岡でもよく見かけます。
花は舌状花がないので目立ちませんがうすいピンクの可愛らしい色をしています。
今日は朝からずっと曇が厚く、肌寒い一日でした。
タグ :植物
2011年11月26日
うしろ姿
通り過ぎた秋のうしろ姿を確認したくなって山道を走ってみました。
「スルガテンナンショウ」の赤いトウモロコシの様な果実が最初に目に付きます。
そして次々に秋の置き土産が現れます。
名前通り葉も白っぽく色付いた「シラキ」。 黄色に色付いているのは「ダンコウバイ」。
触ると臭い、花の終わった「ナギナタコウジュ」。
道に落ちているのは「ムクロジ」の実、中の黒く固い種を羽付きの用の玉にします。
「ケンポナシ」の実の付いた小枝も落ちています。この肥厚した果軸は食べられると云う事になっているので半信半疑、口にしてみました。確かに少し甘味はありますが渋くて食用とは言い難いような ・・・。
赤い実を沢山付けているのにまだ葉が青々している「サルトリイバラ」。 光の具合によって濃い緑色から黒に見える「スイカズラ」の丸い実。
そして「イイギリ」は初冬の陽を受けて枝いっぱいに赤い実をぶら下げていました。
午後のひと時、様々な後ろ姿を見送る事が出来ました。
スルガテンナンショウ

ダンコウバイ
ナギナタコウジュ
左ケンポナシ、右ムクロジ
サルトリイバラ
スイカズラ
イイギリ
「スルガテンナンショウ」の赤いトウモロコシの様な果実が最初に目に付きます。
そして次々に秋の置き土産が現れます。
名前通り葉も白っぽく色付いた「シラキ」。 黄色に色付いているのは「ダンコウバイ」。
触ると臭い、花の終わった「ナギナタコウジュ」。
道に落ちているのは「ムクロジ」の実、中の黒く固い種を羽付きの用の玉にします。
「ケンポナシ」の実の付いた小枝も落ちています。この肥厚した果軸は食べられると云う事になっているので半信半疑、口にしてみました。確かに少し甘味はありますが渋くて食用とは言い難いような ・・・。
赤い実を沢山付けているのにまだ葉が青々している「サルトリイバラ」。 光の具合によって濃い緑色から黒に見える「スイカズラ」の丸い実。
そして「イイギリ」は初冬の陽を受けて枝いっぱいに赤い実をぶら下げていました。
午後のひと時、様々な後ろ姿を見送る事が出来ました。
スルガテンナンショウ

ダンコウバイ

ナギナタコウジュ

左ケンポナシ、右ムクロジ

サルトリイバラ

スイカズラ

イイギリ

タグ :植物
2011年11月25日
「鹿の子」
サネカズラ

竹林に絡み付いた『サネカズラ』が隠れるように赤い実をぶら下げていた。
この赤い粒が沢山付いた丸い形を見ると、色こそ違うが幼い頃母が時折買ってきた和菓子の「鹿の子」が思い出される。
この実は雌花の花床の部分が球状にふくれ、その周りに小さな果実が付いた「集合果」で、乾燥させたものを咳どめや強壮剤として利用しました。
マツブサ科サネカズラ属に分類されますが、かってはマツブサ属と共にモクレン科に
含まれていました。別名は「ビナンカズラ」

竹林に絡み付いた『サネカズラ』が隠れるように赤い実をぶら下げていた。
この赤い粒が沢山付いた丸い形を見ると、色こそ違うが幼い頃母が時折買ってきた和菓子の「鹿の子」が思い出される。
この実は雌花の花床の部分が球状にふくれ、その周りに小さな果実が付いた「集合果」で、乾燥させたものを咳どめや強壮剤として利用しました。
マツブサ科サネカズラ属に分類されますが、かってはマツブサ属と共にモクレン科に
含まれていました。別名は「ビナンカズラ」
タグ :植物
2011年11月23日
ぬばたま
ヒオウギ果実

昼過ぎまで時折日も差していたが、予報通り雨になった。
水路のふちに植えられた『ヒオウギ』が黒い実を付けていた。この黒くツヤのある果実は「ヌバタマ」とか「ウバタマ」と呼ばれ、万葉に登場する事でも知られている。
丘陵地や山麓の乾いた草地に生える多年草だが案外野生種に出会う事は少ない。
アヤメ科に分類されるが、雌しべの一部に特徴があるので一属一種の「ヒオウギ属」に分類されている。
和名は葉の様子が檜の薄板で作った扇を広げた形に似ている事から「檜扇」となりました。

昼過ぎまで時折日も差していたが、予報通り雨になった。
水路のふちに植えられた『ヒオウギ』が黒い実を付けていた。この黒くツヤのある果実は「ヌバタマ」とか「ウバタマ」と呼ばれ、万葉に登場する事でも知られている。
丘陵地や山麓の乾いた草地に生える多年草だが案外野生種に出会う事は少ない。
アヤメ科に分類されるが、雌しべの一部に特徴があるので一属一種の「ヒオウギ属」に分類されている。
和名は葉の様子が檜の薄板で作った扇を広げた形に似ている事から「檜扇」となりました。
タグ :植物
2011年11月22日
8の字
オオジシバリ


今朝の気温は今季最低との事だが、日向に出ると案外とポカポカ。
このところ更に春の花がふえて来て「ナズナ」「ハハコグサ」「オオジシバリ」なども花を付けた。
『オオジシバリ』の花をよく見ると花柱(雌しべの先端)が8の字のような形に見える。
これは他の花から花粉が貰えなかった時、同花受粉をする為に花柱の先がクルリと巻いたもの。 種を守るための安全装置と言える。
「大地縛り」の名は「ジシバリ」に似て花や葉が大きい事からついた。
明日は「小雪」、北風が木の葉を払い、わずかながら雪もみられる頃。と云う事になっているが、静岡はその範ちゅうには入らないようだ。


今朝の気温は今季最低との事だが、日向に出ると案外とポカポカ。
このところ更に春の花がふえて来て「ナズナ」「ハハコグサ」「オオジシバリ」なども花を付けた。
『オオジシバリ』の花をよく見ると花柱(雌しべの先端)が8の字のような形に見える。
これは他の花から花粉が貰えなかった時、同花受粉をする為に花柱の先がクルリと巻いたもの。 種を守るための安全装置と言える。
「大地縛り」の名は「ジシバリ」に似て花や葉が大きい事からついた。
明日は「小雪」、北風が木の葉を払い、わずかながら雪もみられる頃。と云う事になっているが、静岡はその範ちゅうには入らないようだ。
タグ :植物
2011年11月21日
垂れ下がる
リンドウ

引き続き快晴だが気温は一気に下がって来た。
久しぶりに林道を少し走ってみると、前回の台風などで崩れたと思われる土砂を路のわきに寄せてある所が何ヶ所もあり、倒木も多く山は荒れています。
それでも路沿いには『リンドウ』「ヤクシソウ」「シラネセンキュウ」「タイアザミ」そろそろ終わりかけの「ノコンギク」と云った秋の後半を彩る花たちが見られます。
なかでも「リンドウ」は個体数も多く、斜面から垂れ下る様に咲いているものや草刈りのあとに咲いた背の低いものまで様々。
リンドウは「竜胆」と書いて漢方薬としても知られていますが、西洋においてもこの苦い根を粉末にしてワインに入れ、肝臓病、胃痛、などに用いられたそうです。


引き続き快晴だが気温は一気に下がって来た。
久しぶりに林道を少し走ってみると、前回の台風などで崩れたと思われる土砂を路のわきに寄せてある所が何ヶ所もあり、倒木も多く山は荒れています。
それでも路沿いには『リンドウ』「ヤクシソウ」「シラネセンキュウ」「タイアザミ」そろそろ終わりかけの「ノコンギク」と云った秋の後半を彩る花たちが見られます。
なかでも「リンドウ」は個体数も多く、斜面から垂れ下る様に咲いているものや草刈りのあとに咲いた背の低いものまで様々。
リンドウは「竜胆」と書いて漢方薬としても知られていますが、西洋においてもこの苦い根を粉末にしてワインに入れ、肝臓病、胃痛、などに用いられたそうです。
タグ :植物
2011年11月18日
丸くなって
キ ヅ タ


コナラの大木に絡み付いた『キズタ』の花が咲き始めた。まだ蕾の方が多いがとりあえずそんな季節になってきた。
別名は「フユズタ」、どちらかと云うとこちらの名前の方が個人的にはすんなり入って来る。
県西部には「アオヅタ」と呼ぶ所もあるがこれは常緑を意味しての名前と思われる。
ウコギ科キズタ属の常緑ツル性の木本で、小さな花が集まり丸くなって咲くが、
こんな咲き方はウコギ科には多い。
花には5枚の花弁があるが真下に反り返るので目立たず黄色い葯を付けた5本の雄しべ
だけがよく目立つ。
「木蔦」の名前は気根を出して樹木や岩の上などに這いあがる事から。


コナラの大木に絡み付いた『キズタ』の花が咲き始めた。まだ蕾の方が多いがとりあえずそんな季節になってきた。
別名は「フユズタ」、どちらかと云うとこちらの名前の方が個人的にはすんなり入って来る。
県西部には「アオヅタ」と呼ぶ所もあるがこれは常緑を意味しての名前と思われる。
ウコギ科キズタ属の常緑ツル性の木本で、小さな花が集まり丸くなって咲くが、
こんな咲き方はウコギ科には多い。
花には5枚の花弁があるが真下に反り返るので目立たず黄色い葯を付けた5本の雄しべ
だけがよく目立つ。
「木蔦」の名前は気根を出して樹木や岩の上などに這いあがる事から。
タグ :植物