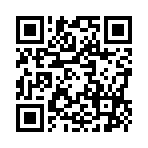2013年04月30日
似て非なる
コメツブウマゴヤシ 若い豆果


コメツブツメクサ 茶色になった花弁に包まれた豆果


大分前から日当たりの良い道端で「コメツブツメクサ」によく似た小さな花を付けていた『コメツブウマゴヤシ』の豆果が形をなして来た。花はよく似ているが、果実を見るとその違いは歴然!
コメツブツメクサは「シャジクソウ属」なので花が終わった後も散らずに残って豆果はその中で成熟するが、コメツブウマゴヤシは「ウマゴヤシ属」と云う事で先端だけ半回転して丸くなった豆果が集まって付き、熟すと黒くなる。
同じマメ科で花の形も大きさも、色もそっくりだが豆果を見ると「似て非なるもの」を
実感する。


コメツブツメクサ 茶色になった花弁に包まれた豆果


大分前から日当たりの良い道端で「コメツブツメクサ」によく似た小さな花を付けていた『コメツブウマゴヤシ』の豆果が形をなして来た。花はよく似ているが、果実を見るとその違いは歴然!
コメツブツメクサは「シャジクソウ属」なので花が終わった後も散らずに残って豆果はその中で成熟するが、コメツブウマゴヤシは「ウマゴヤシ属」と云う事で先端だけ半回転して丸くなった豆果が集まって付き、熟すと黒くなる。
同じマメ科で花の形も大きさも、色もそっくりだが豆果を見ると「似て非なるもの」を
実感する。
2013年04月29日
父子草
チチコグサ


土手斜面に『チチコグサ』が並んでいた。花弁が無くて控えめな花だが茶褐色の総苞片と花序の下に星形に出る苞葉が目立つ。
表面はうすく、裏面には綿毛が密生するので白っぽく見える点はハハコグサと似ているが、花期にも根生葉が有り、匐枝を出してふえる点はハハコグサと異なる。
キク科ハハコグサ属の多年草。名前は「ハハコグサ」に対して付けられた。
明日で4月も終わり、今年も三分の一が過ぎてしまった・・・とりあえずもう寒の戻りもないだろう・・・。


土手斜面に『チチコグサ』が並んでいた。花弁が無くて控えめな花だが茶褐色の総苞片と花序の下に星形に出る苞葉が目立つ。
表面はうすく、裏面には綿毛が密生するので白っぽく見える点はハハコグサと似ているが、花期にも根生葉が有り、匐枝を出してふえる点はハハコグサと異なる。
キク科ハハコグサ属の多年草。名前は「ハハコグサ」に対して付けられた。
明日で4月も終わり、今年も三分の一が過ぎてしまった・・・とりあえずもう寒の戻りもないだろう・・・。
2013年04月27日
水路のふち
オオカワジシャ


以前本流の水辺に繁茂していた『オオカワジシャ』今日は流れを引きこんだ
水路の縁でクレソンなどと共に花盛りを迎えている。
ヨーロッパからアジアにかけての原産と云われ水辺の好きな多年草。
ゴマノハグサ科と云う事で花は形も大きさも「オオイヌノフグリ」とよく似ているが少し色が白っぽい。条件が良ければよく育ち高さは1m程になる。
我国に入って来たのははっきりしないが1926年頃ではないかと云われている。
関東から中部地方の水辺が分布の中心。


以前本流の水辺に繁茂していた『オオカワジシャ』今日は流れを引きこんだ
水路の縁でクレソンなどと共に花盛りを迎えている。
ヨーロッパからアジアにかけての原産と云われ水辺の好きな多年草。
ゴマノハグサ科と云う事で花は形も大きさも「オオイヌノフグリ」とよく似ているが少し色が白っぽい。条件が良ければよく育ち高さは1m程になる。
我国に入って来たのははっきりしないが1926年頃ではないかと云われている。
関東から中部地方の水辺が分布の中心。
2013年04月26日
片側に
タツナミソウ


南西の風が時折強くふくが気温が高めなのでそれ程苦にならない。
東向きの土手斜面、所々に小さな青紫色が黄色主体の中にアクセントを付けるように姿を見せ始めた『タツナミソウ』です。
昨年は5月に入ってから取りあげているが、花の状態からするとほぼ平年通りと云った所でしょうか!
花穂の片側に立ち上がるように唇形花が沢山つく様子が、浮世絵に出てくる
浪頭を連想させるので「立浪草」となったようです。
シソ科タツナミソウ属の多年草。民間では強壮剤などとして用いられるようです。


南西の風が時折強くふくが気温が高めなのでそれ程苦にならない。
東向きの土手斜面、所々に小さな青紫色が黄色主体の中にアクセントを付けるように姿を見せ始めた『タツナミソウ』です。
昨年は5月に入ってから取りあげているが、花の状態からするとほぼ平年通りと云った所でしょうか!
花穂の片側に立ち上がるように唇形花が沢山つく様子が、浮世絵に出てくる
浪頭を連想させるので「立浪草」となったようです。
シソ科タツナミソウ属の多年草。民間では強壮剤などとして用いられるようです。
2013年04月25日
黄色く染めて
ミヤコグサ


『ミヤコグサ』が土手斜面を黄色く染めるようになった。この季節フィールドでは黄色い花が主流でその代表のタンポポは一段落して冠毛を付けた茎を伸ばしている。
その後を引き継ぐ様に「ニガナ」と「ミヤコグサ」が勢力を広げているが、
この2種に勝るとも劣らず勢力を広げているのが「コメツブツメクサ」その名の通り
小さな花を無数に付け、数に物を言わせてこちらも斜面を黄色く染めています。
タンポポとニガナはキク科、コメツブツメクサとミヤコグサはマメ科の多年草です。
やっと気温が戻り厚い上着と決別です。


『ミヤコグサ』が土手斜面を黄色く染めるようになった。この季節フィールドでは黄色い花が主流でその代表のタンポポは一段落して冠毛を付けた茎を伸ばしている。
その後を引き継ぐ様に「ニガナ」と「ミヤコグサ」が勢力を広げているが、
この2種に勝るとも劣らず勢力を広げているのが「コメツブツメクサ」その名の通り
小さな花を無数に付け、数に物を言わせてこちらも斜面を黄色く染めています。
タンポポとニガナはキク科、コメツブツメクサとミヤコグサはマメ科の多年草です。
やっと気温が戻り厚い上着と決別です。
2013年04月23日
葉が丸い
マルバウツギ


いつもの山裾で『マルバウツギ』が一斉に咲き始めた。ウツギより葉が丸いので
この名がある。
ウツギとよく似て葉はザラつくが、花のつく枝では葉柄が無く茎を抱く事や、
花もウツギより平開する点などで見分けられる。
その他に雄しべの花糸の形を比べて見ると更にはっきりする。
ユキノシタ科ウツギ属の落葉低木で関東以西、四国、九州に分布する日本固有種。
今日も厚着をしてフィールドに出た、なかなか暖かさが戻らない。明日は一日雨らしい。


いつもの山裾で『マルバウツギ』が一斉に咲き始めた。ウツギより葉が丸いので
この名がある。
ウツギとよく似て葉はザラつくが、花のつく枝では葉柄が無く茎を抱く事や、
花もウツギより平開する点などで見分けられる。
その他に雄しべの花糸の形を比べて見ると更にはっきりする。
ユキノシタ科ウツギ属の落葉低木で関東以西、四国、九州に分布する日本固有種。
今日も厚着をしてフィールドに出た、なかなか暖かさが戻らない。明日は一日雨らしい。
2013年04月22日
くっきりと
ホタルカズラ


フィールドから河口側に少し下がった土手斜面、伸び始めた草の中から浮かび上がるようにくっきりと『ホタルカズラ』の花が咲いています。「ホタル・・・」の名前が何となくうなづける気がする咲き方です。
花は毎年見る事は出来ますが中々丁度良い時にぶつからないのが世の常で、その点今年はタイミングがうまく合った部類に入るようだ。
ムラサキ科イヌムラサキ属の多年草、花のあと長い走出枝を出し、翌年その先に新苗を作ります。
花の感じとは裏腹に葉にも粗い毛が多く、触るとひどくザラつく。
若葉寒が長引いて今日も寒い。


フィールドから河口側に少し下がった土手斜面、伸び始めた草の中から浮かび上がるようにくっきりと『ホタルカズラ』の花が咲いています。「ホタル・・・」の名前が何となくうなづける気がする咲き方です。
花は毎年見る事は出来ますが中々丁度良い時にぶつからないのが世の常で、その点今年はタイミングがうまく合った部類に入るようだ。
ムラサキ科イヌムラサキ属の多年草、花のあと長い走出枝を出し、翌年その先に新苗を作ります。
花の感じとは裏腹に葉にも粗い毛が多く、触るとひどくザラつく。
若葉寒が長引いて今日も寒い。
2013年04月21日
しずくを
ツルウメモドキ

雄 花
昨夜からの雨は昼前には上がったが、気温は全く上がらず曇天下で結構寒い。
山裾の藪に絡んだ『ツルウメモドキ』は葉に雨のしずくを残しつつ地味な花を沢山付けている。
ウメモドキに似てツル性なのでこの名が付いた。ツルは他の木に絡んでかなり高い所まで登るが花の頃は他の緑に紛れて案外目立たない。
ニシキギ科ツルウメモドキ属で雌雄別株。そしてこの花は雄花なのでこのツルにはきれいな果実は付かない事になる。

雄 花

昨夜からの雨は昼前には上がったが、気温は全く上がらず曇天下で結構寒い。
山裾の藪に絡んだ『ツルウメモドキ』は葉に雨のしずくを残しつつ地味な花を沢山付けている。
ウメモドキに似てツル性なのでこの名が付いた。ツルは他の木に絡んでかなり高い所まで登るが花の頃は他の緑に紛れて案外目立たない。
ニシキギ科ツルウメモドキ属で雌雄別株。そしてこの花は雄花なのでこのツルにはきれいな果実は付かない事になる。
2013年04月16日
粘液を
ノアザミ

東向き土手斜面に『ノアザミ』のトップランナーが姿を見せた。これから次々とその数を増し、紆余曲折(草刈り)を経て秋口まで咲き続ける事でしょう。
アザミの仲間は似ているものが多く、識別に手を焼きますがその多くは夏から秋が中心で春に咲くものはこの辺りではノアザミだけ。 そして総苞片は反りかえらず
粘液を出して粘るのがノアザミの特徴です。
アザミと聞いて誰しも頭に浮かぶのは鋭い刺、昔トゲの事を「アザ」と云い「トゲの有る実体」なのでアザミとなった。と云う説が有ります。
キク科アザミ属の多年草でアザミ属は北半球に250種程も有る大きなグループと云われています。

東向き土手斜面に『ノアザミ』のトップランナーが姿を見せた。これから次々とその数を増し、紆余曲折(草刈り)を経て秋口まで咲き続ける事でしょう。
アザミの仲間は似ているものが多く、識別に手を焼きますがその多くは夏から秋が中心で春に咲くものはこの辺りではノアザミだけ。 そして総苞片は反りかえらず
粘液を出して粘るのがノアザミの特徴です。
アザミと聞いて誰しも頭に浮かぶのは鋭い刺、昔トゲの事を「アザ」と云い「トゲの有る実体」なのでアザミとなった。と云う説が有ります。
キク科アザミ属の多年草でアザミ属は北半球に250種程も有る大きなグループと云われています。
2013年04月15日
赤く変化
ペラペラヨメナ

水路の縁に張り付いている『ペラペラヨメナ』はほぼ一年を通して花を付けているが本来のシーズンは夏から秋にかけて、気温の上昇と共にその勢いが随分と増した。
この草は何故か石垣とかこの様な側面が好きなようで、この水路沿いでは結構増えているが他ではあまり見かけない。
原産地は中央アメリカで鑑賞用に導入されたが60年程前から野生化が知られるようになったようです。
花の色は始めは白色ですが時間が経つと赤く変化するので一つの株に2色の花が付くように見える。

水路の縁に張り付いている『ペラペラヨメナ』はほぼ一年を通して花を付けているが本来のシーズンは夏から秋にかけて、気温の上昇と共にその勢いが随分と増した。
この草は何故か石垣とかこの様な側面が好きなようで、この水路沿いでは結構増えているが他ではあまり見かけない。
原産地は中央アメリカで鑑賞用に導入されたが60年程前から野生化が知られるようになったようです。
花の色は始めは白色ですが時間が経つと赤く変化するので一つの株に2色の花が付くように見える。