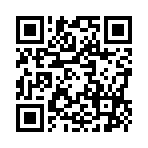2017年07月01日
下を向いて
オオバジャノヒゲ


本日は観察会、雷予報の空を気にしながら皆さんと川沿いの林道を行き、少しだけ草木の能書きをたれさせて頂きました。
いつも思う事ですが多勢(本日は13名)の目には敵わないという事、今日も下見で気がつかなかった花が3個もみつかりました。その内の一つが『オオバジャノヒゲ』足元の草陰に隠れる様にたたずんでいました。普通この草は群生するタイプですが本日はお一人さまでした。
キジカクシ科ジャノヒゲ属の多年草。花茎の高さは14~26センチほどで花は下を向いて咲く。
2017年06月03日
利用価値の
サンショウ 若い果実

6月は青い季節、そこここに若い果実が見られ『サンショウ』も径5ミリ程の
若い果実を沢山付けています。
この果実は一個の花柄に2個がくっついて付く「分果」で果皮にはくぼんだ腺点が多数あります。
サンショウは利用価値の高い木でこの若い果実も「実山椒」と呼ばれ佃煮にされます。
ミカン科サンショウ属の落葉低木で雌雄別株。別名は「ハジカミ」
今日は観察会、皆さんとのんびり一回りしました。気温も大分上がりましたが、木陰のあるコースなので助かりました(参加者15名)
2017年05月06日
左巻き
フ ジ

今日は皆さんと池の近辺をはいかいしてきました。
予報では午後は雨が降るような事になっていましたが、まさかのピーカンで気温は急上昇、汗を拭き拭き日陰を求めて進む事に。雨は困るがピーカンは行き過ぎ、
曇り止まりにしてほしかった。
草も木も花時のものが多く一行の足は遅々として進まず、進行担当としては少々汗の量が増えました。
池の縁のアカメガシワに絡んだ『フ ジ』が中々の画になっていると思って撮ってみたが案の定凡画に。
マメ科フジ属のツル性落葉木本で日本固有種。ツルは左巻き。
2017年03月11日
そのまま名前に
ミツマタ

今日は皆さんと林道の入り口を少し覗いて来ました。
今年は春が遅れていてやっとフサザクラやアブラチャンが咲き始め、『ミツマタ』も
外側から黄色く開花を始めていました。
ご存じ和紙の原料で枝が三つ叉、三つ叉と分枝していく様がそのまま名前になった。葉は花が散った後に展開し、果実は夏にかけて緑色に熟します。
ジンチョウゲ科ミツマタ属の落葉低木で原産地は中国からヒマラヤ。
2016年10月01日
下向きの
ヤブマメ

近くの山には霧がかかり、空気はしっとりとして雨の気配を十二分に感じる中、8人の強者?は何食わぬ顔でやって来ました。
今日はマメ科に絞って2時間ほどの観察会、幸い雨は避けてくれたようです。
帰り際、土手横の藪に絡んだ『ヤブマメ』が花をつけ始めていました。多少遅れ気味のようだがこれから至る所で見かける事になるでしょう。
マメ科ヤブマメ属でツル性の一年草。茎に下向きの毛が生えている。
2016年08月06日
説明し難い
ホドイモ 花


暑い最中の観察会、いかがなものかと思いつつも9名の参加を得て、日陰をたどりながら予定通り進行。
「ニガクサ」の観察中、誰かが「これ何?」と指さす先に『ホドイモ』の花が咲き始めていました。
何度も下見をしたのに気づかなかったが、やはり沢山の人の目は時折喜びをもたらしてくれる。
ホドイモはマメ科ホドイモ属のツル性多年草で花は小さい上曲がりくねっていて
説明し難い形をしているがそれでも初めて見る人が殆どでひとしきり盛り上がりました。
2016年03月05日
一番早く
アオイスミレ

今日は啓蟄、虫も這い出て来る頃との事。そんな虫の尻を押すように気温は上がって四月並、風も無く快適な観察会日和となりました。
この時期野山の変化は著しく、下見の時は見られなかった『アオイスミレ』や「ジロボウエンゴサク」が咲き始めていました。
アオイスミレは丸い葉が「フタバアオイ」の葉に似ているとの事でこの名が付いたようです。スミレの仲間では一番早く咲き、普通あまり花茎を伸ばさないがこの個体は珍しく少しのびている。手前の丸い葉は越冬葉。
2015年10月03日
青い果実
オオバウマノスズクサ 青い果実

まれにみる好天に恵まれて今日は皆さんと一回りして来ました。
水辺では風に揺れるススキが季節をものがたり、そのススキに巻き付いたヤブマメやヤブツルアズキの花がささやかに色を添えています。
見慣れた草花が続く中、誰かが「オオバウマノスズクサ」の若い果実を見つけて一盛り上がり。
このツル植物、花は時々見かけるのですが意外と果実に会えなくて私も初見、と云う事で一枚撮らせて頂きました。
2015年08月01日
汗の量が
ニガガシュウ

暑さに挑戦して来ました。観察会、さすがに参加者は7名と半減しましたが0では有りませんでした。
イグサとコゴメイの違いを確かめたりニガガシュウやオモダカの花を見ながら進みましたが、汗の量が半端ではありません。
約1時間半、夏の湿地は堪えました。
2015年06月06日
着 生
クモラン

今日は梅雨入り前の観察会。昨日の雨が朝まで残って心配したが昼前には何とか見通しが付いた。
今までとは違い何かと制約の有る身体で皆さんに気を使わせてしまったが、取りあえず予定通り進行する事が出来た。
最後にKさんと梅の枝に着生している『クモラン』の確認に行ってみた。以前に比べると個体数は確実に減っている。
交代で覗き込むと小さなツボミが出ていた。もう少しすると筒型の花が咲きますがその長さは約2ミリで色は薄緑色、絶対に気づかれる事のない花です。
※写真が逆さまに見えますがこれはクモランが枝の下側に着生しているためです。