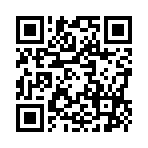2019年10月03日
3ミリ弱
ミチヤナギ



カラスノゴマやツリフネソウと同じように盛んに花を付けているのは道端に沿って生えている『ミチヤナギ』。 花は緑色でふちに白いフリルをあしらったようなよく見ると小洒落た作りです。
しかし如何にせん小さすぎる!草丈は10~40cmで葉腋にくっつくように咲く花の径は3ミリ弱、と云う事でほとんどの人は咲いている事にさえ気づかないと思う。
したがって花を愛でると云う行為には腰をかがめると云う労力が必要となります。
タデ科ミチヤナギ属の一年草で道端や荒れ地に生え、葉がヤナギの葉に似ていると云う事で「道柳」名が付いたようです。
2016年04月15日
植込みで
ニセカラクサケマン


道路の植え込みを中心に今年も『ニセカラクサケマン』が花を付けていた。
この花を最初に見たのは2007年1月、三松のお寺の駐車場の隅で絡まりあって
繁茂していた。
その後そこは工事が入って無くなってしまったが、どっこい近くの植え込みでしっかりと命をつないでいた。
最初は帰化植物図鑑に違う名前で載っていたりして和名が分かるまでかなりの月日を要する事になったのを覚えている。
ケシ科の越年草で原産地は地中海沿岸と云われている。
2016年03月29日
若葉と共に
コクサギ 雄株

雄花序

山際の道端にズラリと並んだ「コクサギ」が打ちそろって若葉と共に小さな花を付けています。
葉や枝に触るとかなりきつい匂いが有りますが生育が活発になるこの時期は特に強く、そばに寄っても匂います。
この匂いを悪臭ととるか否かは個人差が有りますが強力である事は確かです。したがって
名前も『小臭木』に。
ミカン科コクサギ属の落葉低木で雌雄別株。ズラリと並んだほとんどが雄株で雌株が見つかりませんでした(1本ずつ調べた訳では有りませんが)
2016年03月25日
道端
マメカミツレ


道端の植え込みに小さくてハッキリしないが帰化植物の図鑑で見たような草が広がっていた。
腰を下ろして覗き込むと細かく切れ込んだ葉と、直径6~7ミリで舌状花の無い
花とも云えない頭花を沢山付けている。どうやら私にとっては初見のようだ!
と云う事で通行人を気にしながら記録写真を撮らせてもらいサンプルを少々頂いて来ました。
帰宅後調べると案の定オーストラリア原産で1940年ごろ入ってきたキク科の『マメカミツレ』と云う事でした。国内では中部以南の都市部で見いだされているようです。
2016年01月02日
アクセント
カラスウリ 果実

陽の落ちかけた山裾、枯れたイタドリに絡んだ『カラスウリ』がいい色を出して、寒々とした冬景色に丁度良いアクセントを付けていました。
ただ俳諧では果実は秋の季語、花は夏の季語になっているようです。
カラスウリは雌雄異株で雄花も雌花もレースを広げたように繊細な花で、日が暮れてから開き夜明け前に萎む。
2015年09月12日
解釈
ゲンノショウコ 紅花タイプ


市内の『ゲンノショウコ』の花は大抵が白色と相場が決まっているが、たま~に紅紫色の花に出会う事がある。
今回も予期せぬ所で小群落にぶつかった。ここは2週間程前に通った所、その時は花が咲いていなかったので気づかなくて当然、しかし今日また足が向いたと云うのは花が呼んでくれたと勝手に解釈している。
一般的には紅花タイプは西日本、白花タイプは東日本と云う事になっている。
2015年05月09日
存在が
ジャケツイバラ


手前の黒いものが去年の豆のサヤ
ここにも、あそこにも、 大きな花序と派手な色。
山間部に向かう車道。 思いがけない所からその存在を教えているのは『ジャケツイバラ』。鋭い刺を持ったマメ科のツル植物で黒い大きな去年の豆のサヤを残したまま花を付けている個体もあります。


手前の黒いものが去年の豆のサヤ

ここにも、あそこにも、 大きな花序と派手な色。
山間部に向かう車道。 思いがけない所からその存在を教えているのは『ジャケツイバラ』。鋭い刺を持ったマメ科のツル植物で黒い大きな去年の豆のサヤを残したまま花を付けている個体もあります。
2015年03月12日
杯状
トウダイグサ


風の強い日が続きます。外出を渋っていましたが、差し迫った所要にきっかけをもらい、出かけたついでに昨年「トウダイグサ」を見た田んぼに寄ってみました。
時期は昨年とほぼ同じですが株数はかなり少なくなったように見えます。それでもあの独特の杯状花序を茎頂に掲げて風に揺れていました。この花序の様子を「燈台」に見立ててこの名前が付いたと云われています。
2015年02月15日
更新
白花タイプのホトケノザ


毎年白花タイプのホトケノザが咲く駐車場の隅を覗いてみました。3~4本と数は少ないものの今年も咲いていました。
よく見ると丸いツボミのうちはピンク色をしているのがわかります。写真では解りませんが花にも薄い色が付け根あたりに見られます。
ホトケノザは2年草と云う事なので毎年見られると云う事は種子で更新している事になります。
何処にでもあるホトケノザですが、この花を見るといつも北の海の「クリオネ」を連想してしまいます。
2014年11月21日
細々と
ノブドウ 果実

クリハラン(ソーラス確認済み)
細々と落ちる滝
家から車で10分ほど、新東名を架けるときに工事用に作った道へ入ってみた。かなり奥が深くその先は前からあった農道につながっていました。
その途中で細々と落ちる小さな滝を見つけたので少し歩いてみました。季節が季節なので望むべきもないが、滝の近くでは「イズセンリョウ」の白濁した実やシダの「クリハラン」が見られ、日当たりの良い林縁では「ノブドウ」が沢山実をつけていました。

クリハラン(ソーラス確認済み)

細々と落ちる滝

家から車で10分ほど、新東名を架けるときに工事用に作った道へ入ってみた。かなり奥が深くその先は前からあった農道につながっていました。
その途中で細々と落ちる小さな滝を見つけたので少し歩いてみました。季節が季節なので望むべきもないが、滝の近くでは「イズセンリョウ」の白濁した実やシダの「クリハラン」が見られ、日当たりの良い林縁では「ノブドウ」が沢山実をつけていました。