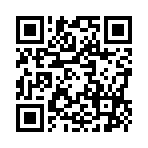2015年01月13日
寒の内でも②
オオイヌノフグリ

もう少し季節が進めば道端や畑の縁などに「これでもか!」と云うほどいたる所で花を見せてくれる『オオイヌノフグリ』ですが、さすがに寒の内ともなると畑の周りを丹念に探してやっとチラホラ見つかる程度でした。
「タチイヌノフグリ」と共に在来の「イヌノフグリ」を山間地に追いやって今や全国制覇を成し遂げた強者でもあります。
2015年01月10日
寒の内にも花
ナズナ


寒の内ともなると河原や土手斜面で花を付けているものはほぼ皆無に等しい。
それでも畑の隅などに目をやると幾つか花を付けている強者も散見される。
そんな中の一つが『ナズナ』またの名はペンペン草、「○○の後はペンペン草も生えない」などと使われる様にあまり環境を選ばない強さを持っているようです。
冷たい風の中、小さな十字花が重なりあって咲いていました。
2013年03月24日
突起が
ノハラツメクサ


土手の桜はほぼ満開になって、初燕も飛来したが多少風が冷たいせいか
思いの外花見客は少ない。
畑の縁では寒い冬の間しばらく姿を消していた『ノハラツメクサ』がオオイヌノフグリを見下しながら咲き広がっていた。
一昨年の12月も押し詰まった寒い日にも細々とながら花を付けていた事を
思えば、全く姿を消してしまった昨年の冬の厳しさがうかがい知れる。
ナデシコ科オオツメクサ属で世界中に帰化しているとの事ですが、草姿は「オオツメクサ」と同じで種子の表面に白色棒状の突起が有るものを「ノハラツメクサ」として区別しています。
線形の葉は対生ですが、葉腋に節間の詰まった短枝を出し、多くの葉が付くので輪生しているように見えます。


土手の桜はほぼ満開になって、初燕も飛来したが多少風が冷たいせいか
思いの外花見客は少ない。
畑の縁では寒い冬の間しばらく姿を消していた『ノハラツメクサ』がオオイヌノフグリを見下しながら咲き広がっていた。
一昨年の12月も押し詰まった寒い日にも細々とながら花を付けていた事を
思えば、全く姿を消してしまった昨年の冬の厳しさがうかがい知れる。
ナデシコ科オオツメクサ属で世界中に帰化しているとの事ですが、草姿は「オオツメクサ」と同じで種子の表面に白色棒状の突起が有るものを「ノハラツメクサ」として区別しています。
線形の葉は対生ですが、葉腋に節間の詰まった短枝を出し、多くの葉が付くので輪生しているように見えます。
2012年09月08日
結局
カラスノゴマ


放置された畑、肥料分が残っていたのだろうか?草たちがすごい勢いで生い茂っている。メヒシバやコセンダングサ、アオジソなどは1mの高さに、オオアレチノギクに至っては2mを超す勢いです。
そんな中に『カラスノゴマ』も混じって花を付けていました。シナノキ科のこの草は同じ科の「ラセンソウ」と共に2009年、2010年に急に身近な所で数多く見かけるようになりましたが、昨年あたりから見かける事が少なくなり結局元の鞘に収まったような気がします。どのような理由なのかはわかりませんが・・・。
草はらの上に漂う「ウスバキトンボ」その上を流れる雲、大分秋の色がつよまって来ました。


放置された畑、肥料分が残っていたのだろうか?草たちがすごい勢いで生い茂っている。メヒシバやコセンダングサ、アオジソなどは1mの高さに、オオアレチノギクに至っては2mを超す勢いです。
そんな中に『カラスノゴマ』も混じって花を付けていました。シナノキ科のこの草は同じ科の「ラセンソウ」と共に2009年、2010年に急に身近な所で数多く見かけるようになりましたが、昨年あたりから見かける事が少なくなり結局元の鞘に収まったような気がします。どのような理由なのかはわかりませんが・・・。
草はらの上に漂う「ウスバキトンボ」その上を流れる雲、大分秋の色がつよまって来ました。
タグ :植物
2012年08月01日
小車
オグルマ


8月に入った。台風も2つあるようだがそんな気配も無く青空が広がり、ジリジリと肌を射す日射しについ日蔭を探してしまう。
手入れの遅れている畑一面に生い茂った「ハキダメギク」をかき分けるようにして
『オグルマ』が昨年にも増して沢山の花を付けた。思いの外、競争力があるようだ。
和名は花を小さな車に見立てて付けられたが、花を上から見ると「小車」と付けられた
名前に合点がいく。
花は「カセンソウ」とよく似ているが、カセンソウの葉は洋紙質でカサカサした感じがする。


8月に入った。台風も2つあるようだがそんな気配も無く青空が広がり、ジリジリと肌を射す日射しについ日蔭を探してしまう。
手入れの遅れている畑一面に生い茂った「ハキダメギク」をかき分けるようにして
『オグルマ』が昨年にも増して沢山の花を付けた。思いの外、競争力があるようだ。
和名は花を小さな車に見立てて付けられたが、花を上から見ると「小車」と付けられた
名前に合点がいく。
花は「カセンソウ」とよく似ているが、カセンソウの葉は洋紙質でカサカサした感じがする。
タグ :植物
2012年07月08日
思案気な
スベリヒユ

茶畑の縁で「スベリヒユ」が咲き始めている。ただ梅雨曇りの昼前の空に、開こうか
開くまいか思案げな顔をしていた。
「スベリヒユ」は逞しい植物で世界中の暖かい地域に普通に見られる雑草として知られているが、飼料や薬草としての側面も持っている。
また夏場の植え込み材料としてよく使われる「ハナスベリヒユ」は同じ種に属する
栽培品です。
スベリヒユ科の仲間は他の植物との競争が少ない所によく生える、その為葉は比較的厚いものが多い。

茶畑の縁で「スベリヒユ」が咲き始めている。ただ梅雨曇りの昼前の空に、開こうか
開くまいか思案げな顔をしていた。
「スベリヒユ」は逞しい植物で世界中の暖かい地域に普通に見られる雑草として知られているが、飼料や薬草としての側面も持っている。
また夏場の植え込み材料としてよく使われる「ハナスベリヒユ」は同じ種に属する
栽培品です。
スベリヒユ科の仲間は他の植物との競争が少ない所によく生える、その為葉は比較的厚いものが多い。
タグ :植物
2012年04月03日
立派な
ムシクサ


雨の降る前に一回りして来ました。畑の端に『ムシクサ』が見事に育っていました。
こんな立派なムシクサは初めて、とは云っても元々小さな草ですから知れていますが高さが
30㌢程も有りました。恐らく畑の肥料を頂いての事と思います。
名前の「虫草」はゾウムシの仲間が子房に卵を産みつけてそこが丸い果実のようになる事が多いのでこの名が付きました。本来の果実の形は小さなハート型をしています。
予報通り昼には降って来ました。外では雷鳴がとどろいています、荒れた天気になってきた。「月にむら雲花に風」


雨の降る前に一回りして来ました。畑の端に『ムシクサ』が見事に育っていました。
こんな立派なムシクサは初めて、とは云っても元々小さな草ですから知れていますが高さが
30㌢程も有りました。恐らく畑の肥料を頂いての事と思います。
名前の「虫草」はゾウムシの仲間が子房に卵を産みつけてそこが丸い果実のようになる事が多いのでこの名が付きました。本来の果実の形は小さなハート型をしています。
予報通り昼には降って来ました。外では雷鳴がとどろいています、荒れた天気になってきた。「月にむら雲花に風」
タグ :植物
2012年01月18日
二段構え
オオイヌノフグリ


風が無いせいか寒中にしてはちょっと得したような日和です。
そんな日向に『オオイヌノフグリ』の花がチラホラと姿を見せ始めました。これも又ごく普通の草ですがしばらくぶりに、それもこんな花の少ない時季に出会うと思わず腰を屈めます。
「オオイヌノフグリ」の花は日が当っている時だけ開き、日が傾くと花はしぼみ出す。
これにより左右に離れていた雄しべは内側に曲げられ、葯が直接柱頭に触れて自家受粉も行われる。したがって虫による受粉との二段構えの受粉法と云う事になる。


風が無いせいか寒中にしてはちょっと得したような日和です。
そんな日向に『オオイヌノフグリ』の花がチラホラと姿を見せ始めました。これも又ごく普通の草ですがしばらくぶりに、それもこんな花の少ない時季に出会うと思わず腰を屈めます。
「オオイヌノフグリ」の花は日が当っている時だけ開き、日が傾くと花はしぼみ出す。
これにより左右に離れていた雄しべは内側に曲げられ、葯が直接柱頭に触れて自家受粉も行われる。したがって虫による受粉との二段構えの受粉法と云う事になる。
タグ :植物