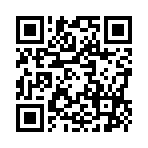2013年08月31日
葉の波の
センニンソウ

8月も最終日台風は消滅したようだが南西の風が強く相変わらず暑い!
土手斜面では「チガヤ」の緑の葉の波の中にツルを延ばした『センニンソウ』が白い花を付け始めた。鮮やかな白が遠くからでもよく目立つ。
河原や家の近所ではこのセンニンソウが多いが少し山の方にいくと葉に鋸歯の有る
「ボタンズル」が多くなる。
キンポウゲ科センニンソウ属のツル性半低木でツルは伸びると3m程になる。 茎や葉には有毒物質を含んでいるが、漢方では根を利尿、鎮痛などに用いる様です。

8月も最終日台風は消滅したようだが南西の風が強く相変わらず暑い!
土手斜面では「チガヤ」の緑の葉の波の中にツルを延ばした『センニンソウ』が白い花を付け始めた。鮮やかな白が遠くからでもよく目立つ。
河原や家の近所ではこのセンニンソウが多いが少し山の方にいくと葉に鋸歯の有る
「ボタンズル」が多くなる。
キンポウゲ科センニンソウ属のツル性半低木でツルは伸びると3m程になる。 茎や葉には有毒物質を含んでいるが、漢方では根を利尿、鎮痛などに用いる様です。
2013年08月30日
あしからず!
トンボソウ

暑さがぶり返して静岡で36,2℃を記録したとの事、暑い訳です。
則沢の林道突き当たりを覗きに行ってみました。 何と林の入り口の小さな流れの縁で腰に蚊取り線香を吊るし新聞を読んでいる先客がいました。話によれば此処の気温は27℃で快適との事、それにしてもこんな所で新聞を読むか・・・。
その奥を少し歩いてみるとヤマホトトギス、ヒメガンクビソウ、ムカゴイラクサ、の花がチラホラ見え、その根元に『トンボソウ』が2本咲いていました。
薄暗い林の中、頑張って見たのですが徒労に終わりました・・・ 。非常に出来の悪い画像ですがとりあえず証拠写真として載せておきます。
。非常に出来の悪い画像ですがとりあえず証拠写真として載せておきます。
ラン科トンボソウ属の多年草。和名は花の姿をトンボに見立てたもので、花をアップで見るとトンボの顔に似ていて面白いのですがこの画像ではそれも無理。あしからず!

暑さがぶり返して静岡で36,2℃を記録したとの事、暑い訳です。
則沢の林道突き当たりを覗きに行ってみました。 何と林の入り口の小さな流れの縁で腰に蚊取り線香を吊るし新聞を読んでいる先客がいました。話によれば此処の気温は27℃で快適との事、それにしてもこんな所で新聞を読むか・・・。
その奥を少し歩いてみるとヤマホトトギス、ヒメガンクビソウ、ムカゴイラクサ、の花がチラホラ見え、その根元に『トンボソウ』が2本咲いていました。
薄暗い林の中、頑張って見たのですが徒労に終わりました・・・
 。非常に出来の悪い画像ですがとりあえず証拠写真として載せておきます。
。非常に出来の悪い画像ですがとりあえず証拠写真として載せておきます。ラン科トンボソウ属の多年草。和名は花の姿をトンボに見立てたもので、花をアップで見るとトンボの顔に似ていて面白いのですがこの画像ではそれも無理。あしからず!
2013年08月27日
絡みついたら
ゴキズル


雄 花
朝から気持の良い青空が広がって暑さも何処となく違う。処暑も過ぎて季節は少しずつ動いているようだ。
通路とハス田の境のてすりやアシに絡み付いた『ゴキズル』は何本ものツルが
絡み合い重なり合って盛り上がっている。
そんな派手に盛り上がった葉の腋にこちらは至って控えめに白い半透明の花が付いています。
雄花も雌花も径は1cm程、ガク片が5枚、花弁も5枚、両方とも同じ様な先のとがった形をしているので花弁が10枚有るように見えます。
これからしばらくの間(10月頃まで)次々と花を咲かせ楕円形の果実を実らせる事でしょう(農薬を掛けられなければの話ですが)
ウリ科ゴキズル属の1年草で雌雄同株。ラグビーボールを小さくしたような果実は熟すと横に割れ、フタの有る器の様になるので「合器蔓」の名が付けられた様です。


雄 花

朝から気持の良い青空が広がって暑さも何処となく違う。処暑も過ぎて季節は少しずつ動いているようだ。
通路とハス田の境のてすりやアシに絡み付いた『ゴキズル』は何本ものツルが
絡み合い重なり合って盛り上がっている。
そんな派手に盛り上がった葉の腋にこちらは至って控えめに白い半透明の花が付いています。
雄花も雌花も径は1cm程、ガク片が5枚、花弁も5枚、両方とも同じ様な先のとがった形をしているので花弁が10枚有るように見えます。
これからしばらくの間(10月頃まで)次々と花を咲かせ楕円形の果実を実らせる事でしょう(農薬を掛けられなければの話ですが)
ウリ科ゴキズル属の1年草で雌雄同株。ラグビーボールを小さくしたような果実は熟すと横に割れ、フタの有る器の様になるので「合器蔓」の名が付けられた様です。
2013年08月26日
花弁は無い
クルマバザクロソウ


雲が多めでいくらか凌ぎ易い気がする。道端の草たちも昨日の雨で大分生気を取り戻したようだ。
地を這って30cm程に茎を広げた『クルマバザクロソウ』が花と実を付けている。白い花弁のように見えるのはガク片でこの花には花弁は無い。
熱帯アメリカ原産で世界の熱帯から温帯にかけて広く帰化しているとの事です。
ザクロソウ科ザクロソウ属の一年草。熟して割れた果実はごく小さいが中からのぞく褐色の種は「ザクロ」の種子に見えなくもない。


雲が多めでいくらか凌ぎ易い気がする。道端の草たちも昨日の雨で大分生気を取り戻したようだ。
地を這って30cm程に茎を広げた『クルマバザクロソウ』が花と実を付けている。白い花弁のように見えるのはガク片でこの花には花弁は無い。
熱帯アメリカ原産で世界の熱帯から温帯にかけて広く帰化しているとの事です。
ザクロソウ科ザクロソウ属の一年草。熟して割れた果実はごく小さいが中からのぞく褐色の種は「ザクロ」の種子に見えなくもない。
2013年08月25日
放射状に
オグルマ


午前中の雨で土手斜面の草たちも一息ついた顔をしている。
畑の端ではコセンダンやオオニシキソウなどと競いながら『オグルマ』が今年も持ちこたえて花を付けていた。
それなりに仲間を増やすのだが時折行われる除草作業の洗礼を受ける為、場所を移しながら命を繋いでいる。
キク科オグルマ属の多年草。放射状に並んだ舌状花の形が小さな車に見えると云う事で「小車」の名が付いたようです。
大気の状態が不安定と云う事で又降り始めました。


午前中の雨で土手斜面の草たちも一息ついた顔をしている。
畑の端ではコセンダンやオオニシキソウなどと競いながら『オグルマ』が今年も持ちこたえて花を付けていた。
それなりに仲間を増やすのだが時折行われる除草作業の洗礼を受ける為、場所を移しながら命を繋いでいる。
キク科オグルマ属の多年草。放射状に並んだ舌状花の形が小さな車に見えると云う事で「小車」の名が付いたようです。
大気の状態が不安定と云う事で又降り始めました。
2013年08月24日
葉がヘラ型
ヘラオモダカ


日射しのないのを見計らって麻機のハス田を覗いて来ました。
ハス田周りの溝では生い茂った夏草に埋もれるように『ヘラオモダカ』が残りの花をチラホラ咲かせていました。花はオモダカに比べると数段小型ですがその代わり花の数は数十倍も有ろうかと思われる程です。
それとオモダカは雄花と雌花に分かれていますが、こちらは両性花です。
オモダカ科サジオモダカ属の多年草。名前は葉がヘラ型をしている事から付けられました。
この溝も草刈りが2m程の所までされていて、明日には此処もきれいさっぱりとなる事でしょう。
近くの溝には「オオアカウキクサ」(シダ植物)も浮いていました。緑色は「アオウキクサ」



日射しのないのを見計らって麻機のハス田を覗いて来ました。
ハス田周りの溝では生い茂った夏草に埋もれるように『ヘラオモダカ』が残りの花をチラホラ咲かせていました。花はオモダカに比べると数段小型ですがその代わり花の数は数十倍も有ろうかと思われる程です。
それとオモダカは雄花と雌花に分かれていますが、こちらは両性花です。
オモダカ科サジオモダカ属の多年草。名前は葉がヘラ型をしている事から付けられました。
この溝も草刈りが2m程の所までされていて、明日には此処もきれいさっぱりとなる事でしょう。
近くの溝には「オオアカウキクサ」(シダ植物)も浮いていました。緑色は「アオウキクサ」

2013年08月23日
元気よく
スベリヒユ

道端、空地、畑、この時季行く先々で見かける『スベリヒユ』。 全体に多肉質で
葉はツヤがあり厚く乾燥に強いので、他の草がしおれそうな真夏の乾ききった地面でも元気よく生育している。
花は夏の日を受けて開き、暗くなると閉じてしまうせいか案外花の咲いているものにぶつかる事が少ない気がする。
スベリヒユ科スベリヒユ属の一年草。開花した花の雄しべに触ると刺激した方に
ゆっくりと曲がる。これは訪れた昆虫に効率よく花粉を託す為の進化の一つと思われる。

道端、空地、畑、この時季行く先々で見かける『スベリヒユ』。 全体に多肉質で
葉はツヤがあり厚く乾燥に強いので、他の草がしおれそうな真夏の乾ききった地面でも元気よく生育している。
花は夏の日を受けて開き、暗くなると閉じてしまうせいか案外花の咲いているものにぶつかる事が少ない気がする。
スベリヒユ科スベリヒユ属の一年草。開花した花の雄しべに触ると刺激した方に
ゆっくりと曲がる。これは訪れた昆虫に効率よく花粉を託す為の進化の一つと思われる。
2013年08月20日
焼いて食用に
ホドイモ

先がピンク色をしているのが翼弁で周りでねじれているのが竜骨弁、この中にシベが入っている。

写りが悪いが竜骨弁からシベが出た状態

午後から所によって一雨有る様な予報だったが所に寄らなかったようで
太陽ギラギラで暑い!そろそろ暑いのにも飽きてきた。
暑いと云えば暑い盛りに咲く『ホドイモ』が気になって出かけて来ました。
この花には何度か挑戦していますが、まともな写真は皆無!言い訳になりますが、花が小さい上に特異な形状をしていてどの角度から撮っていいものやら、
開花状態によってもシベが見えたり見えなかったりでお手上げです。
マメ科ホドイモ属でツル性の多年草。地下に塊根があって焼いて食用にする。
名前の”ホド”は塊を指す言葉のようです。

先がピンク色をしているのが翼弁で周りでねじれているのが竜骨弁、この中にシベが入っている。

写りが悪いが竜骨弁からシベが出た状態

午後から所によって一雨有る様な予報だったが所に寄らなかったようで
太陽ギラギラで暑い!そろそろ暑いのにも飽きてきた。
暑いと云えば暑い盛りに咲く『ホドイモ』が気になって出かけて来ました。
この花には何度か挑戦していますが、まともな写真は皆無!言い訳になりますが、花が小さい上に特異な形状をしていてどの角度から撮っていいものやら、
開花状態によってもシベが見えたり見えなかったりでお手上げです。
マメ科ホドイモ属でツル性の多年草。地下に塊根があって焼いて食用にする。
名前の”ホド”は塊を指す言葉のようです。
2013年08月19日
バラ科なんて
ワレモコウ


午後、一雨来たかなと思っている内に止んでしまい、お湿りにもならない
雨だった。
そんな雨のあとの気持の良い風に『ワレモコウ』が揺れている。この花は私の頭の中では秋そのもので、暑い盛りの中にもこの花を見ると秋のイメージが一気に
広がります。
バラ科ワレモコウ属の多年草。何度となく云ったり書いたりしたと思うがこの花がバラ科なんてと毎年最初に見るたびに思う。穂状に密集した小さな花には花弁は無く4個のガク片が花のように見え、雄しべは4個で葯は黒い。
葉は奇数羽状複葉で小葉は長楕円形の特徴のある整った形をしていて葉だけでもワレモコウとわかる。


午後、一雨来たかなと思っている内に止んでしまい、お湿りにもならない
雨だった。
そんな雨のあとの気持の良い風に『ワレモコウ』が揺れている。この花は私の頭の中では秋そのもので、暑い盛りの中にもこの花を見ると秋のイメージが一気に
広がります。
バラ科ワレモコウ属の多年草。何度となく云ったり書いたりしたと思うがこの花がバラ科なんてと毎年最初に見るたびに思う。穂状に密集した小さな花には花弁は無く4個のガク片が花のように見え、雄しべは4個で葯は黒い。
葉は奇数羽状複葉で小葉は長楕円形の特徴のある整った形をしていて葉だけでもワレモコウとわかる。
2013年08月18日
長毛を密生
ガガイモ


水路の縁のススキに絡んだ『ガガイモ』、いささか「カナムグラ」に押され気味だが
とりあえず花を付けた。
昨年の晩秋に沢山の袋果を付け種髪のついた種が見られた所です。今年は少し
勢いが弱いようだ。
ガガイモ科ガガイモ属でツル性の多年草。花は径1cm程で花冠の内側に長毛を密生し、雄しべ5本が雌しべと合生し長いくちばしをもった柱頭だけが花冠の外にのび出している。この雄しべと雌しべがくっ付き合ったものを「ずい柱」と呼び、
ガガイモ科の重要な特徴となっている。


水路の縁のススキに絡んだ『ガガイモ』、いささか「カナムグラ」に押され気味だが
とりあえず花を付けた。
昨年の晩秋に沢山の袋果を付け種髪のついた種が見られた所です。今年は少し
勢いが弱いようだ。
ガガイモ科ガガイモ属でツル性の多年草。花は径1cm程で花冠の内側に長毛を密生し、雄しべ5本が雌しべと合生し長いくちばしをもった柱頭だけが花冠の外にのび出している。この雄しべと雌しべがくっ付き合ったものを「ずい柱」と呼び、
ガガイモ科の重要な特徴となっている。