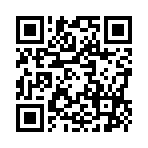2013年12月31日
赤々と
サルトリイバラ

今年もあっという間の大晦日、一夜明ければ新たな年が始まります。
のんべんだらりとした生活の心を新たにするための句読点。
先人達の知恵がしのばれます。
草に明け草に暮れたような一年でしたが、ある意味では幸せだったのかも知れません。
葉が落ちて明るくなったコナラの林床、こちらも葉を落とした『サルトリイバラ』の赤い実が冬の陽に赤々ともえていました。初夏に咲く控えめな花とは対照的です。

今年もあっという間の大晦日、一夜明ければ新たな年が始まります。
のんべんだらりとした生活の心を新たにするための句読点。
先人達の知恵がしのばれます。
草に明け草に暮れたような一年でしたが、ある意味では幸せだったのかも知れません。
葉が落ちて明るくなったコナラの林床、こちらも葉を落とした『サルトリイバラ』の赤い実が冬の陽に赤々ともえていました。初夏に咲く控えめな花とは対照的です。
2013年12月29日
残霜
霜のフユイチゴの葉

今年も残すところあと2日、年が改まると思えばやはり大掃除ならぬ中掃除の一つもと、始めてみたものの普段の手抜きがたたって思いの外時間がかかる。
延長戦は必至だ。
スッキリとした青空は広がっているものの寒い日です。午後になっても日蔭の山道では霜がそのまま残ってフユイチゴの葉を白く彩っていました。
辺りの空気は凛として身が引き締まります。

今年も残すところあと2日、年が改まると思えばやはり大掃除ならぬ中掃除の一つもと、始めてみたものの普段の手抜きがたたって思いの外時間がかかる。
延長戦は必至だ。
スッキリとした青空は広がっているものの寒い日です。午後になっても日蔭の山道では霜がそのまま残ってフユイチゴの葉を白く彩っていました。
辺りの空気は凛として身が引き締まります。
2013年12月25日
十両
ヤブコウジ

師走半ばを過ぎても昔のように忙しなそうな雰囲気はあまり感じない昨今
です。
穏やかな日和の林縁に赤い実がチラホラと目に付きます。センリョウ、マンリョウ、と並んで縁起物の寄せ植えなどにも使われる『ヤブコウジ』です。千両、万両に対し十両と呼ばれたりします。
ヤブコウジ科ヤブコウジ属の常緑小低木。赤い実は微かに甘いがほとんど無味との事です。

師走半ばを過ぎても昔のように忙しなそうな雰囲気はあまり感じない昨今
です。
穏やかな日和の林縁に赤い実がチラホラと目に付きます。センリョウ、マンリョウ、と並んで縁起物の寄せ植えなどにも使われる『ヤブコウジ』です。千両、万両に対し十両と呼ばれたりします。
ヤブコウジ科ヤブコウジ属の常緑小低木。赤い実は微かに甘いがほとんど無味との事です。
2013年12月24日
頂きの紅が
クチベニタケ

風も穏やかでコナラやクヌギの道はポカポカと気持がいい。ガマズミやコバノガマズミの赤い実が沢山残っているのは、野鳥たちの「味好みランキング」で
あまり上位に入っていないのかも知れない?
昨日話の途中に出てきた『クチベニタケ』、気になったのでのぞきに来ました、以前に見た所です。
もう大多数のものは胞子を吐き出して萎んでいる中、一個だけまだ赤い口紅を付けたままのものがありました。
直径1cm程の小さなキノコですが頂きの紅が何とも愛らしくユーモラスな姿です。名前もキノコの表情をうまくとらえたよいネーミングだと思います。

風も穏やかでコナラやクヌギの道はポカポカと気持がいい。ガマズミやコバノガマズミの赤い実が沢山残っているのは、野鳥たちの「味好みランキング」で
あまり上位に入っていないのかも知れない?
昨日話の途中に出てきた『クチベニタケ』、気になったのでのぞきに来ました、以前に見た所です。
もう大多数のものは胞子を吐き出して萎んでいる中、一個だけまだ赤い口紅を付けたままのものがありました。
直径1cm程の小さなキノコですが頂きの紅が何とも愛らしくユーモラスな姿です。名前もキノコの表情をうまくとらえたよいネーミングだと思います。
2013年12月23日
冬季に一段と
アカウキクサ


麻機のハス田では正月用のレンコン掘りが盛んです。寒い中、体半分が隠れるほど掘り起こしての作業は見るからに重労働の様です。
そのそばの水湿地で『アカウキクサ』が水面を被っていました。
小型浮遊性のシダで植物体は少し赤みを帯びるが、冬季には一段と鮮やかに赤くなります。
よく似ている「オオアカウキクサ」とは水中に垂れ下った根に毛がある事で
見分ける事が出来る。 小さいので解り難いが少し持ち帰って、ガラスのコップに浮かべると横から見れるのでよく解る。


麻機のハス田では正月用のレンコン掘りが盛んです。寒い中、体半分が隠れるほど掘り起こしての作業は見るからに重労働の様です。
そのそばの水湿地で『アカウキクサ』が水面を被っていました。
小型浮遊性のシダで植物体は少し赤みを帯びるが、冬季には一段と鮮やかに赤くなります。
よく似ている「オオアカウキクサ」とは水中に垂れ下った根に毛がある事で
見分ける事が出来る。 小さいので解り難いが少し持ち帰って、ガラスのコップに浮かべると横から見れるのでよく解る。
2013年12月22日
開閉する
ツチグリ

山際の切り通し状の所に『ツチグリ』が数個散らばっていました。
ツチグリの外皮は成熟すると星形に開きますが、湿度により開閉する様に
なっています。少し乾いてきたようで、この個体も大分丸まり始めています。
ツチグリ科のキノコで中央の丸い所に雨粒などが当たると頂部の小穴
から胞子が煙のように噴き出る仕組みです。
今日は「冬至」暦によれば「ウツボグサ」の芽の出る頃との一項が有る。
長い冬をじっと耐え、春が来たら真っ先に葉を伸ばすための準備なのでしょうか、 野の草の逞しさに感服です!

山際の切り通し状の所に『ツチグリ』が数個散らばっていました。
ツチグリの外皮は成熟すると星形に開きますが、湿度により開閉する様に
なっています。少し乾いてきたようで、この個体も大分丸まり始めています。
ツチグリ科のキノコで中央の丸い所に雨粒などが当たると頂部の小穴
から胞子が煙のように噴き出る仕組みです。
今日は「冬至」暦によれば「ウツボグサ」の芽の出る頃との一項が有る。
長い冬をじっと耐え、春が来たら真っ先に葉を伸ばすための準備なのでしょうか、 野の草の逞しさに感服です!
2013年12月17日
白いものが
キヅタ

放置された畑の縁に植わっているサクラに絡んだ『キズタ』が花を付けている、
早いのもはすでに青い実になっているから大分おくての個体のようだ。
しかしよく見ると何だか変です、随分白く見えるので近づいてみると、花それぞれに雪が積もった様に白い何かがくっ付いています。何だか解らないので持ち帰ってピンセットで触ると塩のようなものがポロリと落ちました。
触ったり突いたり匂いを嗅いだりしましたが結局謎は解けず、投げ出す事に。
また明日考えよう!

放置された畑の縁に植わっているサクラに絡んだ『キズタ』が花を付けている、
早いのもはすでに青い実になっているから大分おくての個体のようだ。
しかしよく見ると何だか変です、随分白く見えるので近づいてみると、花それぞれに雪が積もった様に白い何かがくっ付いています。何だか解らないので持ち帰ってピンセットで触ると塩のようなものがポロリと落ちました。
触ったり突いたり匂いを嗅いだりしましたが結局謎は解けず、投げ出す事に。
また明日考えよう!
2013年12月16日
利用法
ノイバラ果実

まわりの葉が落ちて藪の中に隠れていた『ノイバラ』の赤い実が初冬の陽に
その存在を知らしめています。
このきれいな赤い実を水窪町の方では下剤に利用すると云う話を聞きました。
食用にならない実でも色々利用法が有るものです、食用と云えばノイバラの若い枝の皮をむいて食べる習慣は全国的にあるとの事、先人たちの食に対するこだわりに脱帽です。
今日は久しぶりに風がおさまって日だまりはポカポカです。

まわりの葉が落ちて藪の中に隠れていた『ノイバラ』の赤い実が初冬の陽に
その存在を知らしめています。
このきれいな赤い実を水窪町の方では下剤に利用すると云う話を聞きました。
食用にならない実でも色々利用法が有るものです、食用と云えばノイバラの若い枝の皮をむいて食べる習慣は全国的にあるとの事、先人たちの食に対するこだわりに脱帽です。
今日は久しぶりに風がおさまって日だまりはポカポカです。
2013年12月15日
引っ掛って
テイカカズラ

今年も『テイカカズラ』が旅立ちの時を迎えています。銀色に光る冠毛が少し引っ掛っていますが今日のこの風なら早晩引き離されて空中散歩が楽しめる事でしょう。
キョウチクトウ科テイカカズラ属で常緑ツル性の木本。茎から気根を出して樹幹や岩壁を登っていきます。
茎や葉を乾燥して煎じたものを解熱や強壮の薬用にする様です。

今年も『テイカカズラ』が旅立ちの時を迎えています。銀色に光る冠毛が少し引っ掛っていますが今日のこの風なら早晩引き離されて空中散歩が楽しめる事でしょう。
キョウチクトウ科テイカカズラ属で常緑ツル性の木本。茎から気根を出して樹幹や岩壁を登っていきます。
茎や葉を乾燥して煎じたものを解熱や強壮の薬用にする様です。
2013年12月14日
ロウ質の
ナンキンハゼ

風が強く寒い日が続きます。そんな中遊水池を少し覗いてみました。
鳥が種を運ぶのでしょうか?此処は実生の『ナンキンハゼ』が多く見られます。
きれいに色付いた葉も落ち、果皮も落ちて白い種子が「塩豆」を振りまいたように
木全体が白く見える程沢山付いて目を引きます。
この白く見えるのはロウ質の仮種皮と呼ばれる部分で種子はその中に包まれています。
トウダイグサ科シラキ属で中国原産の落葉高木。花は地味で目立ちませんが、
紅葉が美しくこの白い種子も見栄えがするので公園や街路樹などによく利用されます。

風が強く寒い日が続きます。そんな中遊水池を少し覗いてみました。
鳥が種を運ぶのでしょうか?此処は実生の『ナンキンハゼ』が多く見られます。
きれいに色付いた葉も落ち、果皮も落ちて白い種子が「塩豆」を振りまいたように
木全体が白く見える程沢山付いて目を引きます。
この白く見えるのはロウ質の仮種皮と呼ばれる部分で種子はその中に包まれています。
トウダイグサ科シラキ属で中国原産の落葉高木。花は地味で目立ちませんが、
紅葉が美しくこの白い種子も見栄えがするので公園や街路樹などによく利用されます。