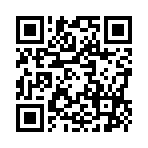2016年11月29日
球形に
キ ヅ タ

絡むところが無くて横に這った『キヅタ』が花をつけていた。周囲を見るとあらかた咲き終わっていて最後の花かも知れない。
球形花序に1cm程の小さな花が集まって付き、それぞれに5本の雄しべが力強く
突き出ている。
葉は切れ込みの有るものと卵型のものが有り、花の咲くような枝では卵型が多く、若い木では3裂する葉が多い。
ウコギ科キヅタ属の常緑つる性木本。別名は「フユヅタ」
2016年11月28日
枝豆風の
ヤブマメ豆果

道端のコセンダングサに絡んで枝豆を小型にしたような豆果を付けているのは『ヤブマメ』 もう少しすると茶褐色に熟し、中に3~5個のウズラ豆を小さくしたような豆を入れる。
マメ科ヤブマメ属のツル性一年草。 豆果の縫合線に黒っぽい伏毛がある。
11月も末、辺りは枯れ草色が増えてきた。
2016年11月23日
毛深さ
ヤブムラサキ

枝や葉、ガクなどに星状毛が密生しているのがわかる

雨こそ落ちてこないが北寄りの風が吹いてかなり寒い。
先日取り上げた「ムラサキシキブ」と共にレンズを向ける事の多い『ヤブムラサキ』。
今年も林縁の枝先から秋波?を送られ、またまた対峙することになった。
「ヤブムラサキ」は枝や葉裏、ガクなどに星状毛や軟毛が密生していて少し近づけばその毛深さがわかる。
クマツヅラ科ムラサキシキブ属の落葉低木。ちなみにムラサキシキブとヤブムラサキの雑種を「イヌムラサキシキブ」という。
2016年11月22日
特有の
ツルグミ


垂れ下がった枝にちょっと異様な花を沢山付けているのは『ツルグミ』。
この花の色はグミの仲間特有の鱗状毛と呼ばれるもので、種によって色や形や数が異なる。
枝がツルのようになるのでこの名前が付いたが巻き付いたりはせず他の木に寄りかかるようにして伸びていきます。
グミ科グミ属のツル性常緑低木。果実は翌年の5月頃赤く熟すが青い内に落ちてしまう事が多い。
2016年11月21日
香りの方は
ヒイラギ 両性花

雄 花

朝から厚い雲に覆われているが何とか持ちこたえてくれた。
池ノ端のヒイラギの老木が今年も花をつけてそばに寄るといい香りがする。
老木になると葉の刺が取れて丸くなるが香りの方は変わらないようだ。
小さな花の雄しべの数は2本と少ない。
モクセイ科モクセイ属の常緑小高木。雌雄別株だが雄株の方が多いように感じる。
この花が咲くと年の瀬も近い。
2016年11月20日
取り合わせが
タンキリマメ


9月に咲いた小さな花が実を結び、赤い鞘が割れて黒い豆が2つずつ顔を出し始めています。接写すると大きく見えますが豆の直径は5~6ミリです。
近所の藪に絡まっている『タンキリマメ』は行きやすい事や鞘の赤色と黒光りする豆の取り合わせが気に入って「トキリマメ」と共に何度となく取り上げることに!
マメ科タンキリマメ属でツル性の多年草。茎は左巻きに絡みつく。
2016年11月18日
見映えのする
サネカズラ

立冬も過ぎて野山は実りの時、様々な草木が実を結んでいるがそんな中で好んでレンズを向けたくなる種とそうでない種が自然とできてしまう。中でも色と云い形と云い見映えのする『サネカズラ』の果実は毎年シャッターを切ってしまう。
マツブサ科サネカズラ属で常緑のツル性木本。名前は漢字にすると「実葛」と書き、
ツル植物で果実がよく目立つ事から付いたと云われている。
2016年11月17日
食用には
ノブドウ



土手下にツルを延ばした『ノブドウ』は微妙に色を変えた実を付けていました。
この実には「ノブドウミタマバエ」などの幼虫が入り込んで虫エイになり大きく膨らむことが多いのですが珍しくこのツルにはそれが無く形がそろっていました。 色がきれいでブドウの仲間ですが食用にはなりません。
ブドウ科ブドウ属のツル性多年草で野山や道端などにごく普通に生えています。
2016年11月16日
晩秋まで
シラネセンキュウ


雲間から時折もれる陽ざしに山裾の『シラネセンキュウ』の白い花が一瞬浮かび上がった。
晩秋まで咲くこの花もそろそろ終盤に入って若い果実を付けている。
名前は日光の白根山から知られ、中国原産の薬草「センキュウ」に似ている事から付いたようです。
セリ科シシウド属の多年草で分布は、本、四、九州。
2016年11月13日
思いは同じ
ムラサキシキブ

気温は暑からず寒からずで気持ちのいい秋晴れが続いている。ただ明日は下り坂のようだが・・・。
山裾の藪から枝を出して『ムラサキシキブ』が淡紫色の果実を付けている。果実の色は多少個体差があってこの個体は少し色がうすい。
クマツヅラ科ムラサキシキブ属の落葉低木。
名前の由来はきれいな果実を「紫式部」にたとえたと云われているが学名のカリカルパも「美しい果実」という意味との事で、どうやら洋の東西を問わず思いは同じだったようです。