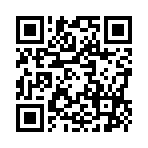2020年08月06日
取り揃えて
タンキリマメ花

豆 果

タ ネ

葉の形

金網に絡んだ『タンキリマメ』が一連の姿を見せていた。
花が咲いて結実して鞘を作り、それがはじけて種まで。同じ所に一式取り揃えているのもちょっと面白いと思って撮ってみました。
ついでに葉の確認用も、葉の質は少し厚めで一番幅の広い所が中央より少し先端によった所になります。これは「トキリマメ」との識別ポイント。
マメ科タンキリマメ属で日当たりの良い所に生えるツル性の多年草。ツルに下向きの毛がある。
2020年06月25日
様々
エゴノキ若い果実


5月15日に満開の花を取り上げた『エゴノキ』は早くも若い果実を沢山ぶら下げていました。
植物は花が咲いてから果実が熟すまでの期間は種によって様々ですが比較的に早い部類に入るかもしれません。
もう少し熟すとカラが縦に割れ、中の種子はヤマガラの大好物、足で押さえて殻を割っている姿を時折見かけました。
ちなみにクスノキ科の「シロダモ」のように翌年の花が咲く頃にやっと前年の実が熟すと云うのんびりタイプも有るようです。


5月15日に満開の花を取り上げた『エゴノキ』は早くも若い果実を沢山ぶら下げていました。
植物は花が咲いてから果実が熟すまでの期間は種によって様々ですが比較的に早い部類に入るかもしれません。
もう少し熟すとカラが縦に割れ、中の種子はヤマガラの大好物、足で押さえて殻を割っている姿を時折見かけました。
ちなみにクスノキ科の「シロダモ」のように翌年の花が咲く頃にやっと前年の実が熟すと云うのんびりタイプも有るようです。
2020年06月05日
アズサ
キササゲ花序


恐らく植栽されたものだと思いますが、金網を隔てた雑木の中で『キササゲ』が咲き始めていました。ただ高い木の上のほうなので無理かと思ったが一房だけ私にも処理できそうな所に咲いていたので撮らせてもらいました。
キササゲは古くに中国から入ってきたと云われ、植栽によく使われていますが、川岸など陽当たりのいい所に野生化もしている様です。
ノウゼンカズラ科キササゲ属の落葉高木で高さは5~15mになります。別名は「アズサ」
2020年05月15日
存在に
エゴノキ 花



この花の存在に気付くのは大抵が林道などに、真ん中がスポッと抜けた花が大量に落ちている時、
頭上を見上げるとまだ花は残っていても大分上の方だったりして結局コンデジを向けずに終わってしまう事になる。
今回は手の届く所に花の落ちる前の個体にお目に掛かることが出来たので無駄なシャッターをこれでもかと切らせて頂きました。
エゴノキ科エゴノキ属の落葉小高木で株立ちになり、高さは7~8m程になる。
少し離れた所ではアオキに絡んだ「スイカズラ」も花盛りになっていました。少しピークを過ぎたようで黄色くなった花が目立ちます。
スイカズラ科スイカズラ属で半常緑のツル性木本。別名は「キンギンカ」
スイカズラ


2018年06月13日
和紙の
ヒメコウゾ 果実


『ヒメコウゾ』がキイチゴに似た美味しそうな果実を付けていた。この果実、甘味は有るがイガイガして口当たりが悪く、味見をした後は食べる気はおきない。
和紙の原料として栽培される「コウゾ」は本種とカジノキの雑種と云われ、本種も古くは織物や和紙の原料に利用されたようです。
クワ科コウゾ属の落葉低木。雌雄同株で新枝の下部の葉腋に雄花、上部の葉腋に雌花が付く。
2018年06月09日
未熟果
ドクウツギ


ドクウツギの果実が赤く鮮やかに色づいて夏が徐々にその体裁を整えつつある。ただドクウツギの果実はこれが完熟ではない。完熟すると深みのある黒でいかにもそれらしい色になる。
ドクウツギ科ドクウツギ属の落葉低木。ドクウツギ科は非常に小さな科でドクウツギ属のみから成り世界に10種ほどしかなく、いずれも猛毒成分を含んでいるとの事です。日本にはドクウツギ1種しか自生していない。
2018年03月18日
変異が
キブシ 雄花序

雄花では黄色い葯の付いたオシべはメシベよりほんの少し長い。ちなみに雌花のオシベは退化して短い。下の画像で確認できる。

林縁の『キブシ』が咲き始めた。咲くと云っても華々しく開花するわけではないがつぼ型の小さな花が連なって日本髪に挿す簪を連想させる。他の草木が遅れている中でこの花はほぼ例年並みと云った所でしょうか。
キブシは北海道西南部から九州まで分布する日本固有種ですが地域的な変異が多く「ナンバンキブシ」「ハチジョウキブシ」「エノシマキブシ」「ナガバキブシ」「コバノキブシ」などが知られています。
キブシ科キブシ属の落葉低木または小高木で雌雄別株。この株は雄株。
2016年09月10日
待っていた?
ノササゲ


林縁のアカメガシワから垂れ下がった『ノササゲ』が丁度良い高さに花を付けていました。風も無くまるで撮られるのを待っていたかのように。
別段変わり映えのしないマメ科の植物ですがどちらかと云うと好きな部類に入ります。日本の固有種と云う事も有るのかも知れない。
ノササゲは野原に生えないので「キツネササゲ」に改名すべきだと云う説もありましたが「野生のササゲ」と理解してそのまま使われています。


林縁のアカメガシワから垂れ下がった『ノササゲ』が丁度良い高さに花を付けていました。風も無くまるで撮られるのを待っていたかのように。
別段変わり映えのしないマメ科の植物ですがどちらかと云うと好きな部類に入ります。日本の固有種と云う事も有るのかも知れない。
ノササゲは野原に生えないので「キツネササゲ」に改名すべきだと云う説もありましたが「野生のササゲ」と理解してそのまま使われています。
2016年06月25日
花期が
ヒヨドリジョウゴ


密生する軟毛

林縁の草地で『ヒヨドリジョウゴ』がツルを延ばし早くも花を付けていた。随分と早い気がするが以前にも他の所で6月中旬に見ているので最近は花期が早まっているようだ。
ナス科ナス属のツル性多年草。花は深く5裂して思い切り反り返る。全体に軟毛を密生してさわるとしっとりとした感じ。
和名は果実をヒヨドリが食べるからとか。 有毒植物。
2015年12月21日
枯れても
ナギナタコウジュ 枯れ姿

小さな滝に向かって枯れた花穂を振りかざしているのは『ナギナタコウジュ』。10月下旬に花を載せましたが花の時より花穂が反り返っていよいよ長刀に見えて来ました。
名前の下半分のコウジュは漢字にすると「香薷」と書き、匂いを意味していて枯れても触ると結構匂います。そしてその匂いが良いか悪いかは意見の分かれる所ではあります。

小さな滝に向かって枯れた花穂を振りかざしているのは『ナギナタコウジュ』。10月下旬に花を載せましたが花の時より花穂が反り返っていよいよ長刀に見えて来ました。
名前の下半分のコウジュは漢字にすると「香薷」と書き、匂いを意味していて枯れても触ると結構匂います。そしてその匂いが良いか悪いかは意見の分かれる所ではあります。