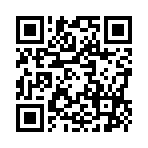2013年04月13日
垂れるような
コゴメウツギ


DS裏の山裾では見慣れた雑木がそれぞれにツボミを付けていますが今日は
『コゴメウツギ』が咲き始めました。
それこそ「何処にでも有る」と云ってもいいほどこの辺りの野山ではよく見かける
木です。
名前は・・・ウツギとなっていますが、バラ科コゴメウツギ属の落葉低木で2m程になり、
幹の先は頭を垂れるような樹形になります。
新しい枝は赤みを帯びていますが古くなると白っぽくなります。
この所肌寒い日が続いて厚手の上着が復活していますが、とりあえず今日までのようです。


DS裏の山裾では見慣れた雑木がそれぞれにツボミを付けていますが今日は
『コゴメウツギ』が咲き始めました。
それこそ「何処にでも有る」と云ってもいいほどこの辺りの野山ではよく見かける
木です。
名前は・・・ウツギとなっていますが、バラ科コゴメウツギ属の落葉低木で2m程になり、
幹の先は頭を垂れるような樹形になります。
新しい枝は赤みを帯びていますが古くなると白っぽくなります。
この所肌寒い日が続いて厚手の上着が復活していますが、とりあえず今日までのようです。
2013年04月11日
口を閉ざした
アマドコロ

午前中から西の風が強く、今日も気温は上がらないようだ。
近所の土手斜面にそろそろ『アマドコロ』が出る頃なのでのぞいてみました。
数は沢山出ていましたが、まだ出始めのようで花はぶら下がっていますが、筒型の花は口を閉ざしたままです。
昨年は25日に取りあげていますがこの時はしっかり開いていましたので一応昨年並みと云う所でしょうか。
ユリ科ナルコユリ属の多年草で、花は3個のガク片と3個の花弁が互いに合着して筒状になり先端部だけ開きます。
花が葉蔭に隠れて見にくい草も有りますが、アマドコロの葉は上に向かって開くので花が良く見えます。

午前中から西の風が強く、今日も気温は上がらないようだ。
近所の土手斜面にそろそろ『アマドコロ』が出る頃なのでのぞいてみました。
数は沢山出ていましたが、まだ出始めのようで花はぶら下がっていますが、筒型の花は口を閉ざしたままです。
昨年は25日に取りあげていますがこの時はしっかり開いていましたので一応昨年並みと云う所でしょうか。
ユリ科ナルコユリ属の多年草で、花は3個のガク片と3個の花弁が互いに合着して筒状になり先端部だけ開きます。
花が葉蔭に隠れて見にくい草も有りますが、アマドコロの葉は上に向かって開くので花が良く見えます。
2013年04月10日
ブラシのような
ヒメハギ


強い西風がふいて体感温度はかなり低い。
土手斜面、枯草やツルボなどの緑が混ざった中に小さな紅紫色の部分が所々目に付く、『ヒメハギ』の花が咲き始めたようだ。
良く見れば15㌢程にのびた茎に若葉と共に鳥が羽を広げたような花を付けている。
花が咲かなければまず気付かれる事はない草だ。
鳥の羽のように左右にのびた一対は5枚有るガク片の内の2枚で、花弁のように紅紫色に染まって発達している。
花弁は3枚で筒状に合着し、下の花弁の先だけが細く切れ込んでいる。
このブラシのような房がどんな働きをするのかは良く解っていない。


強い西風がふいて体感温度はかなり低い。
土手斜面、枯草やツルボなどの緑が混ざった中に小さな紅紫色の部分が所々目に付く、『ヒメハギ』の花が咲き始めたようだ。
良く見れば15㌢程にのびた茎に若葉と共に鳥が羽を広げたような花を付けている。
花が咲かなければまず気付かれる事はない草だ。
鳥の羽のように左右にのびた一対は5枚有るガク片の内の2枚で、花弁のように紅紫色に染まって発達している。
花弁は3枚で筒状に合着し、下の花弁の先だけが細く切れ込んでいる。
このブラシのような房がどんな働きをするのかは良く解っていない。
2013年04月09日
先端が球状に
スルガテンナンショウ

今日も遊木の森を少し歩いて来ました。足元にはカラスノエンドウを筆頭に見慣れた草花が何処までも続き『スルガテンナンショウ』も数多く姿を見せています。
スルガテンナンショウは仏炎苞の中の付属体の先端が球状に膨らみ前に曲がるのが特徴です。
サトイモ科テンナンショウ属の多年草で、この仲間は生える地方によって少しずつ形態が変化して様々な種に分かれています。
この「スルガテンナンショウ」は中部地方の太平洋側に分布が限られ伊豆を除く県内の他は、岐阜県と愛知県のみに分布が知られています。
暑くなし寒くなし、青い空には瑞々しい若葉が映えて自然と心が軽くなるのがわかります。

今日も遊木の森を少し歩いて来ました。足元にはカラスノエンドウを筆頭に見慣れた草花が何処までも続き『スルガテンナンショウ』も数多く姿を見せています。
スルガテンナンショウは仏炎苞の中の付属体の先端が球状に膨らみ前に曲がるのが特徴です。
サトイモ科テンナンショウ属の多年草で、この仲間は生える地方によって少しずつ形態が変化して様々な種に分かれています。
この「スルガテンナンショウ」は中部地方の太平洋側に分布が限られ伊豆を除く県内の他は、岐阜県と愛知県のみに分布が知られています。
暑くなし寒くなし、青い空には瑞々しい若葉が映えて自然と心が軽くなるのがわかります。
2013年04月08日
細々と
イヌノフグリ


山間の民家の石垣「細々と消え入りそうな・・・」そんな言葉がぴったりな風情で『イヌノフグリ』が花を付けていました。
外来の「オオイヌノフグリ」や「タチイヌノフグリ」に追いやられたのか、あるいは人間様に追われたのか?定かではないが、近年はとんと見かけなくなってしまった「イヌノフグリ」です。
情報をもらって訪ねて見ましたが、青い空のもと小さな花が殊更小さく小さく見えました。


山間の民家の石垣「細々と消え入りそうな・・・」そんな言葉がぴったりな風情で『イヌノフグリ』が花を付けていました。
外来の「オオイヌノフグリ」や「タチイヌノフグリ」に追いやられたのか、あるいは人間様に追われたのか?定かではないが、近年はとんと見かけなくなってしまった「イヌノフグリ」です。
情報をもらって訪ねて見ましたが、青い空のもと小さな花が殊更小さく小さく見えました。
2013年04月07日
お誂え向き
ホウチャクソウ


昨夜来の雨は予報に反し朝には上がって晴れ間も見えるが、時折の強風は
かなりのものです。
近所の土手、桜並木の根元付近に『ホウチャクソウ』が花を付けていました。
此処は3年ほど前から時々通る所ですが、今回初めて気が付いた。
普通地味な花が下を向いて咲きますが、今日はお誂え向きに斜め横を向いている
花が有り、中のシベを楽に撮る事が出来ました。
ユリ科チゴユリ属の多年草。
和名は寺院の軒先などに下げる「宝鐸」に花の形を見立てたようです。
県内には「ホトケユリ」の方言名も有るそうです。


昨夜来の雨は予報に反し朝には上がって晴れ間も見えるが、時折の強風は
かなりのものです。
近所の土手、桜並木の根元付近に『ホウチャクソウ』が花を付けていました。
此処は3年ほど前から時々通る所ですが、今回初めて気が付いた。
普通地味な花が下を向いて咲きますが、今日はお誂え向きに斜め横を向いている
花が有り、中のシベを楽に撮る事が出来ました。
ユリ科チゴユリ属の多年草。
和名は寺院の軒先などに下げる「宝鐸」に花の形を見立てたようです。
県内には「ホトケユリ」の方言名も有るそうです。
2013年04月05日
細くピンとして
マキノスミレ

春の嵐の前の穏やかな日和、遊木の森を歩いて来ました。
タンポポの黄色とクサイチゴの白い花が一面に広がって春の野を彩っています。
所々で群落を作っているのはタチツボスミレ、フモトスミレも小さいながらそれなりに
自己主張しています。少し盛りは過ぎたようだが『マキノスミレ』もチラホラと控えめに花を付けていました。
このスミレは西日本に多い「シハイスミレ」の変種と云われ、東日本に多く分布している。そして近畿地方にはその中間型が多く分布しているようです。
マキノスミレの葉は細くピンとして裏はわずかに紫色を帯びる程度で、花の後は淡くなります。
稜線では「ヤマツツジ」も咲きだしていました。

春の嵐の前の穏やかな日和、遊木の森を歩いて来ました。
タンポポの黄色とクサイチゴの白い花が一面に広がって春の野を彩っています。
所々で群落を作っているのはタチツボスミレ、フモトスミレも小さいながらそれなりに
自己主張しています。少し盛りは過ぎたようだが『マキノスミレ』もチラホラと控えめに花を付けていました。
このスミレは西日本に多い「シハイスミレ」の変種と云われ、東日本に多く分布している。そして近畿地方にはその中間型が多く分布しているようです。
マキノスミレの葉は細くピンとして裏はわずかに紫色を帯びる程度で、花の後は淡くなります。
稜線では「ヤマツツジ」も咲きだしていました。
2013年04月04日
突き出た
ムラサキケマン


山裾の道端で『ムラサキケマン』が林立していました。場所によっては盛りを過ぎた感の所も有りますが、此処はまだ盛りです。
深く切れ込んだ葉と共に紅紫色の花はよく目立ちます。
ケシ科キケマン属の2年草。この属の花は後ろに突き出た距を持つ独特の形をしている。
全草にアルカロイドを含み有毒で、茎を折ったりするといくらか悪臭が有る。


山裾の道端で『ムラサキケマン』が林立していました。場所によっては盛りを過ぎた感の所も有りますが、此処はまだ盛りです。
深く切れ込んだ葉と共に紅紫色の花はよく目立ちます。
ケシ科キケマン属の2年草。この属の花は後ろに突き出た距を持つ独特の形をしている。
全草にアルカロイドを含み有毒で、茎を折ったりするといくらか悪臭が有る。
2013年04月02日
地を這って
カキドオシ


今日は朝から雨が降ったりやんだりとはっきりしないので、出るのをやめました。 と云う事で今回は昨日撮った『カキドオシ』を載せました。
フィールド近辺には何ヶ所かミカン畑が有りますが、そのミカン畑も一様ではなく
しっかり手が入っている畑、時折手が入る畑、あるいはほぼ放置された畑など様々です
そんな中に畑の持主がミカンの木の下に草が生えるのを容認しているとしか思えない畑があり、その一画を毎年一時「カキドオシ」の花が彩ります。したがって必然的に此処も巡回コースに加わる事となりました。
カキドオシは花が終わると茎が地を這って広がり、その様が垣根も通す程なので「垣通し」の名が付きました。
シソ科カキドオシ属の多年草。 茎や葉を揉むとよい香りがする。


今日は朝から雨が降ったりやんだりとはっきりしないので、出るのをやめました。 と云う事で今回は昨日撮った『カキドオシ』を載せました。
フィールド近辺には何ヶ所かミカン畑が有りますが、そのミカン畑も一様ではなく
しっかり手が入っている畑、時折手が入る畑、あるいはほぼ放置された畑など様々です
そんな中に畑の持主がミカンの木の下に草が生えるのを容認しているとしか思えない畑があり、その一画を毎年一時「カキドオシ」の花が彩ります。したがって必然的に此処も巡回コースに加わる事となりました。
カキドオシは花が終わると茎が地を這って広がり、その様が垣根も通す程なので「垣通し」の名が付きました。
シソ科カキドオシ属の多年草。 茎や葉を揉むとよい香りがする。
2013年04月01日
群がって
ヒトリシズカ


この間から気になっていた『ヒトリシズカ』を確認に千代を覗いて来ました。
葉が完全に開く直前で「大事なものを両の手で優しく包むような感じ」の姿が並んでいる所を撮りたかったのですが、ちょっと遅れてしまいました。残念!
それはともかくとして今年も無事に姿を見る事が出来て一安心です。
それから今年新たに気付いた事ですが、一本の花茎に花序が二つ付いている個体も有ると云う事です。(画像では前の2株がその個体です)
センリョウ科センリョウ属の多年草で名前とは裏腹に群がって出る事が多い。


この間から気になっていた『ヒトリシズカ』を確認に千代を覗いて来ました。
葉が完全に開く直前で「大事なものを両の手で優しく包むような感じ」の姿が並んでいる所を撮りたかったのですが、ちょっと遅れてしまいました。残念!
それはともかくとして今年も無事に姿を見る事が出来て一安心です。
それから今年新たに気付いた事ですが、一本の花茎に花序が二つ付いている個体も有ると云う事です。(画像では前の2株がその個体です)
センリョウ科センリョウ属の多年草で名前とは裏腹に群がって出る事が多い。