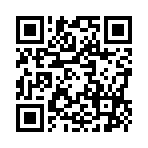2015年10月19日
直立する
ヒキオコシ

花は長さ6ミリ前後

日当たりの良い斜面に『ヒキオコシ』が小さな花を沢山付けて風に揺れています。
ヒキオコシはシソ科ヤマハッカ属の多年草。この仲間の花は唇形花で上唇が直立する特徴が有ります。
葉や茎には苦味成分があって昔から胃腸病の民間薬として利用されてきました。
気がつけば随分と日も詰まって寒露も末候、戸口で虫の無く頃とか。しかしコンクリートの箱のような所に住んでいれば虫も演奏にはやって来ないようだ。
2015年10月18日
株数の割に
キチジョウソウ


この所あまり吉事はなかった、と云うかその反対の事の方が多かったが「吉事が有ると咲く」と云う伝説に由来の『キチジョウソウ』は素知らぬ顔で咲き始めていました。漢字にすると「吉祥草」と書きます。
地表を這う茎でふえ、しばしば群落を作りますが株数の割に花を付ける株は少ない。
分類はユリ科からDNA分類ではキジカクシ科に移されました。
2015年10月17日
個性派
ダイモンジソウ


「個性派がいるらしいよ!」と云うお話を頂いて早速行ってみました。
『ダイモンジソウ』 水が滴る岩壁が白く見える程沢山咲いています。この中から個性派を見つける事が出来るだろうか?と一瞬危惧しましたが、それは意外と簡単に見つかりました。
花弁に大きなキョ歯が付いたような、ささくれた様な確かに個性派です。初めて見ますが、これも変種の一つになるのでしょうか?、
?の多いこの頃です。
2015年10月14日
寄りかかって
ヤマトリカブト


民家に近い荒れた林縁、毎年気を揉みながら覗きに行く。
サラシナショウマが長い茎の先につぼみを付けていたが葉は何故か一部が残っているだけ? 3株程になってしまったオクモミジハグマは残念ながら花が終わっていた。
『ヤマトリカブト』は寝そべったり寄りかかったりしながらではあるが5~6株が花を付けていた。やれやれだ。
それではとコンデジを構えると風の機嫌が悪く、しばし花の前で固まる事となる。
2015年10月13日
それなりに
ゴキズル

果実は上下2つに割れる

道端の手すりに絡んだ『ゴキズル』が最後の大盤振る舞いといった風情で果実と共に
沢山の花を付けている。
果実は蓋が取れてすでに種が落ちた後のものも有り、青い果実も横に筋が入り二つに分かれる準備が進んでいる。
果実の中には大きめの種が2個並んで入っている。
秋空の元、ゴキズルもそれなりに実りの時を迎えていた。
2015年10月12日
そのまま残る
アキノウナギツカミ


秋の空は一点の曇りなくまさに快晴そのもの!見上げただけでこちらの心も晴れる。
土手下の側溝で『アキノウナギツカミ』が広がっている。枝先に小さな花を金平糖のように付けているが花期も終盤とみえて開花しているものは少ない。この花、花が済んだ後も花被はそのまま残り果実を包んでいるのでツボミがいつまでも有るように見える。ただ一度咲いたものは上半部の色が濃く、白っぽいツボミと多少異なる。
2015年10月11日
免れた
ウスベニニガナ

空き地の真ん中でポツリ、ポツリと色を置いたように咲いているのは『ウスベニニガナ』可愛らしい色をしているが舌状花が無いというのが致命的で花扱いされない事も多々ある。
ただ同じような仲間のベニバナボロギクやダンドボロギク、ノボロギクのように「ボロギク」と云う命名を免れたのは可愛らしい色のせいかも知れない。
暖かい静岡では道端や河原などでほぼ一年中見られるが、何処にでもあると云う訳では無い。
2015年10月10日
紅 葉
タコノアシ

渡りの途中の「ノビタキ」の姿が目に付くようになって高い山からは紅葉の話題も聞こえて来るようになりました。
蓮田の横の湿地では『タコノアシ』が負けじと見事に紅葉して目を引いています。
名前が名前なので「ゆでだこ」に似た形の花序を探してみましたが残念ながら思い通りにはいきません。
タコノアシは図鑑によって「ユキノシタ科」と「ベンケイソウ科」を行ったり来たり。決め手に欠ける作りの様です。
2015年10月09日
風媒花
カナムグラ 雄花序

雌花序

ツルを延ばし一面に広がっているのは『カナムグラ』ツル植物では5本の指に入る強者です。
道端や荒れ地、土手などにごく普通にに見られるのでついつい見ないふりをしてきましたが、今日は雄株の少し離れた所に雌株もあったので取り上げて見ました。
カナムグラは風媒花、雄花は細く短い花糸の先に大きめの葯が付いて少しの風でも揺れて花粉を振りまき、雌花は苞の間から出た糸のような柱頭には毛が多く花粉をひっかけて捉えるように出来ています。
名前は漢字にすると「金葎」で茎が鉄のように丈夫でよく繁る草の意味との事です。
2015年10月06日
早くも
カラスノゴマ

今年は河原林の『カラスノゴマ』は昨年に比べると随分と数が少なて勢いがない。
早くも果実を形成して店じまいの準備に入った個体もある。
栄枯盛衰はどこでもあるが河原においては特に激しいようだ。
外来種などでは一年で消えていくものも有って、「イモネホシアサガオ」や「ヤンバルミチヤナギ」などは今年は姿が見られなかった。