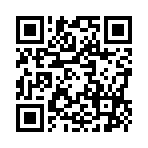2019年05月11日
変化が
コミヤマスミレ


葉裏は紫色を帯びる

気温は上がって日中は暑い程になった。車もエアコン始動です。
数あるスミレの中でも花期のもっとも遅いスミレの一つと云われている『コミヤマスミレ』の様子を見に行ってみました。
林道脇の崩れそうな斜面に点々と咲いていましたが若干ピークは過ぎたようで花の新鮮味は今一と云った所です。それと暗めの所が好きな事でも知られたスミレと云う事でコンデジ片手に大苦戦!
スミレ科スミレ属で葉の表面の色は変化が激しく、斑入のものもある。裏面は紫色を帯びるがこれも濃淡の変化が多い。 日本特産種でガク片が反り返る特徴が有る。
2019年05月06日
蜜源植物
ハリエンジュ



足久保の猿

大きくなると15m程にもなると云うから幹も細いしこの木はまだほんの駆け出しのようだが溢れんばかりの花を付けているのは『ハリエンジュ』
丁度橋の下から生えていたので至近距離で花を撮る事が出来た。良い香りがあって蜜源植物としても知られている。
マメ科ハリエンジュ属の落葉高木で北アメリカ原産。別名はニセアカシア。
2019年05月05日
小さな科
ミツバウツギ花序と葉

花の間に「ハナグモ♀」が潜んでいる


林縁の『ミツバウツギ』の花が盛りを迎えている。
先日のコゴメウツギがそうであったようにこの木も「ウツギ」と入っているがウツギの仲間ではありません。
こうして見るとウツギの名を冠した植物は思いの他多い。それだけウツギ自体が世間一般に広く浸透している事かも知れない。
花には芳香があり花弁はオシベとメシベを囲んで直立し、開いているのはガク片。
ミツバウツギ科ミツバウツギ属の落葉低木。世界に30種ほどの小さな科です。
2019年04月29日
普通種
コゴメウツギ


ここに来て肌寒い日が続いていささか戸惑いを覚える。
近所の山裾では「マルバウツギ」や『コゴメウツギ』が咲き始めている。両方ともよく見る普通種だが花が咲けばそれなりに華やぐ。
コゴメウツギはウツギの名が入っているがウツギの仲間ではありません。
バラ科コゴメウツギ属の落葉低木で叢生し、花は花弁もガク片も白いが長い方が花弁で短い方がガク片です。
2019年04月25日
一花弁が
シャク


若い果実

西日のあたる林縁で『シャク』が小さな白い花を付けている。花としてはすでに後半で果実になっている所も多々ある。
この時季、葉だけ見ると恐ろしくよく似ている「ヤブジラミ」が成長してくるのでかなり紛らわしくなる。
セリ科シャク属の多年草。小散形花序の周囲の花は外側の一花弁が大きくなる。
2019年04月23日
越年草
ミヤマキケマン


葉の形状

林道脇斜面の『ミヤマキケマン』は10センチ程の総状花序に黄色い花を沢山付けている。
この仲間はよく似ていて紛らわしいが近縁種の「フウロケマン」の総状花序の長さは2~5センチ程と短く、花の数も少ない。花の形も後ろに突き出した距の曲がりが少し大きい事などで識別される。
ケシ科キケマン属の越年草(秋に発芽して冬を越し、春になってから花が咲き、結実し、夏までに枯れるもの)
2019年04月22日
葉の裏は
ヒメウツギ

花糸の翼は上部が広がって先がとがる

4月も半ばを過ぎて気温の高い日が多くなって、今日も汗ばむほどです。
谷筋では「ガクウツギ」のツボミが目に付くようになり、『ヒメウツギ』はすでにしっかりと咲いています。
この花は名前が示すように「ウツギ」より少し優しい感じがします。葉の裏は無毛で他のウツギの仲間との識別ポイントになります。
ユキノシタ科ウツギ属の落葉低木。高さは1.5m程の株立ち。
2019年04月15日
栄養が
ウラシマソウ


林の中や林縁など比較的半日陰で見かける事の多い『ウラシマソウ』ですが山裾の結構な陽の当たる場所にも姿を見せていました。そのせいか葉の形が日陰のものより細く感じます。
サトイモ科テンナンショウ属の多年草。雌雄別株だが性転換する。初め雄株だが地下の球茎に栄養が貯まってくると雌株になる。
2019年04月07日
蜜弁
トウゴクサバノオ


そろそろツバメの初見が取り沙汰される頃になって気温もグッと上がりました。車は窓を全開です。
そんな陽気に誘われて『トウゴクサバノオ』の様子を見に行ってみましたが残念、どうやら遅きに失したようです、開いているのは1個だけ、後は皆つぼんでいました。と云う事で今回唯一無二の花です。
キンポウゲ科シロカネソウ属の多年草。花は直径8ミリ程で花弁状に見えるのはガク片。本来の花弁は蜜の分泌を専業とする黄色い蜜弁になっています。


そろそろツバメの初見が取り沙汰される頃になって気温もグッと上がりました。車は窓を全開です。
そんな陽気に誘われて『トウゴクサバノオ』の様子を見に行ってみましたが残念、どうやら遅きに失したようです、開いているのは1個だけ、後は皆つぼんでいました。と云う事で今回唯一無二の花です。
キンポウゲ科シロカネソウ属の多年草。花は直径8ミリ程で花弁状に見えるのはガク片。本来の花弁は蜜の分泌を専業とする黄色い蜜弁になっています。
2019年04月06日
深山樒
ミヤマシキミ


林道わきの木陰で『ミヤマシキミ』が咲きだしていた。びっしり付いたツボミの一部が開いている。
これは雄花で4本のオシベが確認できます。雌花にもオシベはありますが退化して小さくて貧弱、蕾の数も少ない。
ミカン科ミヤマシキミ属の常緑低木。雌雄別株で葉にアルカロイドを含む。